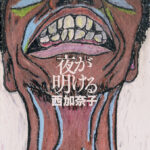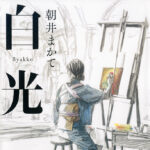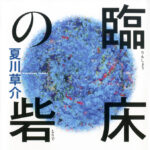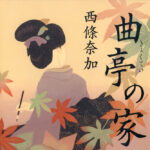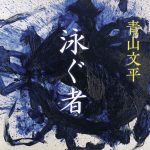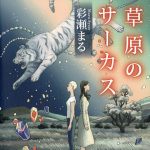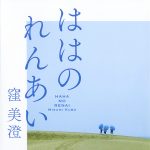内藤麻里子の文芸観察
内藤麻里子の文芸観察(26)
若者にこんな思いをさせてはいけない。西加奈子さんの『夜が明ける』(新潮社)を読んで、つくづくそう感じた。ロスト・ジェネレーションの若者を描いているのだが、『漁港の肉子ちゃん』(2011年)、『サラバ!』(2014年)などで知られる西作品らしく、不思議な企(たくら)みに満ち、なおかつ心に迫る小説だ。
内藤麻里子の文芸観察(25)
名古屋出入国在留管理局の施設で、スリランカ人の女性が亡くなったのは2021年3月のこと。ずっと体調不良を訴えていたにもかかわらず、放っておかれた末の死だった。死亡事件はほかに何件も発生しているだけでなく、長期にわたる不当な収容、難民申請の驚くほど低い認定率など入管をめぐるニュースはたびたび耳にしてきた。中島京子さんの『やさしい猫』(中央公論新社)は、そんな現状に一石を投じる長編小説だ。
内藤麻里子の文芸観察(24)
朝井まかてさんの『白光』(文藝春秋)は、夢に向かって生きることの野心と挫折と、その果てにある充足が余すことなく詰まっている。生きるとはこういうことよと、ゆうゆうたる筆遣いでつづる画業小説だ。描かれるのは日本初のイコン(聖像)画家、山下りんの生涯である。
内藤麻里子の文芸観察(23)
ベストセラーとなった『神様のカルテ』(2009年)で知られる夏川草介さんは、長野県在住の現役医師でもある。そんな夏川さんの『臨床の砦』(小学館)は、自身が直面したコロナ診療の実態を看過できず、“緊急出版”した小説だ。ここに至って過去最多の感染者を出している現状に、物語から大きな警鐘が鳴り響いてくる。
内藤麻里子の文芸観察(22)
『島はぼくらと』(2013年)、『かがみの孤城』(2017年)など少年、少女を描いて定評のある辻村深月さんが、『琥珀の夏』(文藝春秋)で新たな舞台に挑戦した。それは、自らは「宗教」と名乗らない設定の、集団生活をする思想団体である。
内藤麻里子の文芸観察(21)
今年1月、『心淋し川』で直木賞を射止めた西條奈加さんの新作が、『曲亭の家』(角川春樹事務所)だ。受賞後第一作となるわけだが、なんとこれが全く新しい時代小説なのだ。思い切って言ってしまえば、フェミニズム時代小説である。
内藤麻里子の文芸観察(20)
残念ながら、21世紀といえども女性は子供の頃から“女”という枠にはめ込まれて育つ。徐々にその枷(かせ)に異を唱える声は沸き起こっているものの、社会は一気には変わらない。『あとかた』(2013年)、『男ともだち』(2014年)などで女性の生きづらさを繊細に描いてきた千早茜さんが、新刊の『ひきなみ』(角川書店)で、繊細さに力強さが加わった物語を紡ぎ出した。
内藤麻里子の文芸観察(19)
青山文平さんの『泳ぐ者』(新潮社)は、異色の時代小説だ。本格ミステリーの形を取って妙味ある謎解きをする縦軸に、主人公が生きる道を模索する横軸が絡み合う。そのどちらからも、現代の私たちの心を奪う光が投げかけられてくる。
内藤麻里子の文芸観察(18)
『やがて海へと届く』(2016年)、『くちなし』(2017年)など、人の思いを繊細につづってきた彩瀬まるさんの新作『草原のサーカス』(新潮社)は、これまでの作品にはめられていた狭い枠が取り払われた。とんでもない試練が襲う大きな物語を構築する中で、生きることとは、仕事とは何かを問いかけてくる。
内藤麻里子の文芸観察(17)
窪美澄さんの『ははのれんあい』(角川書店)は、どこにでもいそうな家族の歳月を柔らかな筆致で描く。出産、死別、離婚など、さまざまな節目を経て変わっていく家族の形を追い、さらにその先を見はるかすような物語になっている。