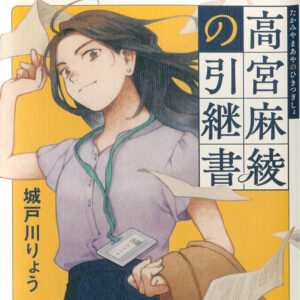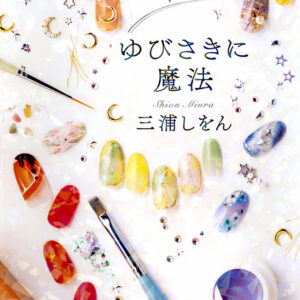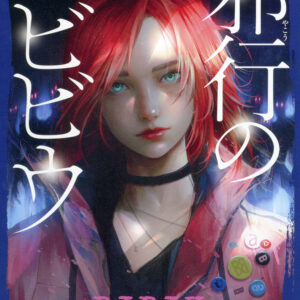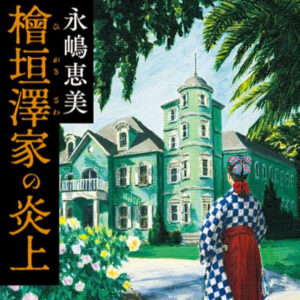内藤麻里子の文芸観察
内藤麻里子の文芸観察(69)
阿部智里さんの『皇后の碧(みどり)』(新潮社)は、これぞ令和に送り出すにふさわしいと言いたくなるようなファンタジー小説である。アニメにもなった和風大河ファンタジー「八咫烏(やたがらす)」シリーズで知られる著者の、新たな挑戦だ。
内藤麻里子の文芸観察(68)
「ブレイクショット」とは、ビリヤードで最初に打つショットのこと。逢坂冬馬さんの『ブレイクショットの軌跡』(早川書房)は、そのショットと同じ名を持つ1台のSUV車が世に放たれ、ビリヤードでボールが飛び散るがごとくあちこちに移動し、それと共に物語が波及していく。現代の闇をさまよう群像が描かれるのだが、もうダメなのかと思った時、かすかな希望が立ち現れる。それはごく簡単なこと、「善良」を取り戻せばいいのだと教えてくれる。静かに胸を打つ会心作と言えよう。
内藤麻里子の文芸観察(67)
いまどきはやりの、キャラクターが立った軽妙なお仕事小説かと思ったら、まったくそんなことはなかった。城戸川(きどかわ)りょうさんの『高宮麻綾(まあや)の引継書』(文藝春秋)は、最初こそ、その雰囲気を漂わせるが、あくの強い主人公が仕事と格闘する姿を描く、かなり本格派のビジネス小説だった。それにポップな衣を着せて、現代が放つビジネス小説と言えよう。うれしい誤算に満ちた快作だ。
内藤麻里子の文芸観察(66)
昨今の小説は派手なアイデアや、特異なキャラクターで読ませる作品が注目されがちだが、平岡陽明さんの『マイ・グレート・ファーザー』(文藝春秋)は、それらとは一線を画す。ファンタジー仕立てであるが、人生の岐路に立った男の姿を静かに、実直に描き、驚くほどじわじわと心にしみてくる。そっと自分の中に取っておきたいような小説だ。
内藤麻里子の文芸観察(65)
今年は戦後80年、そこでこんな本を選んでみた。伊吹亜門さんの『路地裏の二・二六』(PHP研究所)は、結果的に陸軍の発言力を強めた二・二六事件を題材にして、その裏で起きていたもう一つの事件を虚実ない交ぜにして描いてみせた歴史ミステリーだ。
内藤麻里子の文芸観察(64)
三浦しをんさんの『ゆびさきに魔法』(文藝春秋)は、爪を美しく彩るネイリストを題材にしている。『神去なあなあ日常』『舟を編む』など、秀逸なお仕事小説を手がけた作家による、新たな充実のお仕事小説だ。
内藤麻里子の文芸観察(63)
暗号通貨やプログラミングのC++言語など、デジタル世界のテクノロジーに関して知識を持ち合わせていない。それなのに読まされてしまうのが、宮内悠介さんの『暗号の子』(文藝春秋)だ。テクノロジーというギミックを使って、現代という時代を描き出す。
内藤麻里子の文芸観察(62)
そういえば、新型コロナウイルス感染症が広がる前、鉄道会社の車庫などに侵入して列車に落書きする事件が相次いでいた。そんなことを思い出させてくれたのが、井上先斗(さきと)さんの『イッツ・ダ・ボム』(文藝春秋)だ。あの時、車体に書かれた文字などはグラフィティと言い、それを記した者をグラフィティライターと呼ぶのだそうだ。グラフィティを街中で目にしたこともおありだろう。斯界(しかい)のスターはバンクシーである。同書はグラフィティおよびグラフィティライターの進化系を描いた物語だ。
内藤麻里子の文芸観察(61)
東山彰良さんの『邪行(やこう)のビビウ』(中央公論新社)は、戦争小説とファンタジーを融合してカジュアルに書いているように見せながら、この作家ならではのどこかいびつで滑稽で、現代に地続きの切迫感を漂わせている。
内藤麻里子の文芸観察(60)
永嶋恵美さんの『檜垣澤(ひがきざわ)家の炎上』(新潮文庫)は、明治末から大正にかけて、横浜の上流社会を生き抜く娘の野望をミステリー仕立てで描いた、濃(こま)やかな物語である。文庫書き下ろしだ。