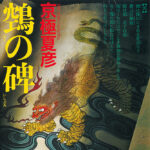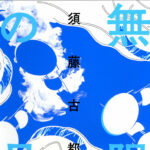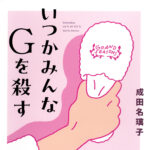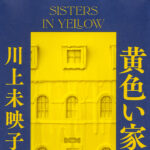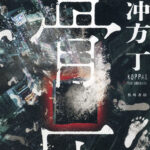内藤麻里子の文芸観察
内藤麻里子の文芸観察(49)
京極夏彦さんは1994年、『姑獲鳥(うぶめ)の夏』で鮮烈なデビューを果たした。以降、怪異が彩る事件の謎を古書肆(こしょし)の主、中禅寺秋彦が解いていく「百鬼夜行」という人気シリーズに成長した。『鵼(ぬえ)の碑(いしぶみ)』(講談社)は同シリーズの17年ぶり、長編10作目となる新作である。いつもの妖しく、惑溺(わくでき)させる雰囲気の中で、新しい時代の息吹を感じられる作品となっている。
内藤麻里子の文芸観察(48)
「総務省の調査によれば、全国の空き家数は二〇一八年の時点で八百四十九万戸だという」。これは重松清さんの『カモナマイハウス』(中央公論新社)で紹介される実態で、今や全国いたるところで空き家が目につく。かく言う私も親がいなくなったら実家をどうしたらいいか、今から不安を抱えている。本書はこの空き家問題と、定年後や子育て、親の介護を終えた後のロス問題に鋭くもコミカルに斬り込んだ。直視しにくい、重いテーマを軽やかに描くことによって、私たちに問題の所在をさらりと見せてくれる。
内藤麻里子の文芸観察(47)
須藤古都離(ことり)さんの『無限の月』(講談社)は、恋愛小説にして手に汗握る大救出劇、そして驚きのSF小説でもある。読み終えて、意識を変えることの難しさを突きつけられたような気がする。
内藤麻里子の文芸観察(46)
成田名璃子さんの『いつかみんなGを殺す』(角川春樹事務所)は、タイトルだけ見た時は本格ミステリーかと思ったが、さにあらず。いやはや豪快なスラップスティック(ドタバタ劇)だった。なにせ「G」とは、見たら誰しも悲鳴を上げてしまうあの昆虫「ゴキ……」のことなのだから。
内藤麻里子の文芸観察(45)
誤解を恐れず言えば、読み終わった時、まさか小説でお芝居が観られるとはという、いささか妙な感慨にふけってしまった。それが永井紗耶子さんの『木挽町(こびきちょう)のあだ討ち』(新潮社)である。
内藤麻里子の文芸観察(44)
砂原浩太朗さんの『藩邸差配役日日控』(文藝春秋)は、藩邸の「差配役」という、現代でいえば会社の“総務部”のような役職を創り出したことがお手柄の時代小説だ。連作短編で日々巻き起こる騒動をつづりながら、底に流れる陰謀を鮮やかに描き出す。
内藤麻里子の文芸観察(43)
犯罪に手を染めたり、犯罪者として糾弾されたりする人々に何が起きていたのか。川上未映子さんの『黄色い家』(中央公論新社)は、なかなか見えてこない彼らの裏側にある一つの類型に切り込んだ。それは、家にいられない少女たちが模索する生きる道であった。
内藤麻里子の文芸観察(41)
「人の振り見て我が振り直せ」を肝に銘じてきた。例えばホームビデオは他人に見せない、会社で後輩をいじめない、過去の自慢話をしない、などだ。最近は「老害」が気になっていた。そこで、内館牧子さんの『老害の人』(講談社)である。
内藤麻里子の文芸観察(40)
新しい年の初回に紹介するのは、冲方丁(うぶかた・とう)さんの『骨灰(こっぱい)』(角川書店)である。ホラー小説なので、新年早々に何をと思われる方もあろうが、私たちが畏れるべきなにものか、触れてはならない存在を鮮烈に描き出している。人間の分をもって暮らすという慎みについて、思わず考えをめぐらせてしまった。