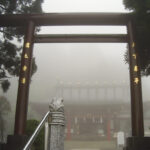寿げない新年
今年ほど、「あけましておめでとうございます」と言って新春を寿(ことほ)ぎたいと思ったことはない。なぜなら、当然に思っていたその祝辞を素直に言うことができないからだ。
続きを読む
この連載の記事一覧
「世界で最も美しい島」パラワンに残留した日本人の末裔たち
パラワン島に刻まれた虐殺の歴史
世界で最も美しい島と評されるフィリピンのパラワン島。南北400キロにわたる細長いこの島は、大自然が手つかずの姿で残ることから“フィリピン最後の秘境”と称され、世界中から観光客が訪れます。しかし、この美しい島には悲しい虐殺の歴史があり、戦後長らく多くの残留日本人二世たちが無国籍のまま取り残されていたことは、近年までほとんど明かされませんでした。
続きを読む
この連載の記事一覧
天候の黒子として雨や熱を運ぶ「風」に感謝し 農耕の無事を神々に祈る
あくまでも個人の主観だが、伊勢地方は他の地域に比べて風がよく吹く印象がある。初めて伊勢を訪れたのが、寒風すさぶ一月末のことで、冬の季節風が吹く時期であったためかもしれない。「神風の」は伊勢を示す枕詞。伊勢は海に面しており、現在では津市の山間部に日本最大級の出力を誇る風力発電所があるほど、地理的にも風が吹き抜けやすい地形にある。とはいえ、「神風の伊勢」とは言い得て妙だと思ったのもその時であった。
続きを読む
この連載の記事一覧
政治的混乱
安倍晋三元首相の国葬が終わってからも、政治の混乱が続いている。政権の支持は続落し、相次いで三人の閣僚が辞任した。一人目の経済再生担当大臣はカルト的宗教との密接な関係が露呈した。二人目の法務大臣は、死刑という人の生死の与奪の権を握っているにもかかわらず、生命の重みに対する識見のなさが指弾された。三人目の総務大臣は、政治資金を所轄する責任者であるにもかかわらず、自らの政治資金問題が次々と露呈した。これらに見られるのは、政治的汚濁そのものだ。
続きを読む
この連載の記事一覧
「助けて」と言える社会は、「つながる力」のある社会
国民の約90%がキリスト教徒であるフィリピン
フィリピンでは国民の約9割がキリスト教徒のため、クリスマスを喜びに満ちた特別な日と受けとめます。イエス・キリストという大いなるプレゼントが世界にもたらされたことをみんなで祝い、喜びを分かち合う――この「分かち合い」の精神こそが、フィリピン社会の底力となっているのです。
続きを読む
この連載の記事一覧
合理性と感情
先月、二〇二二年の出生数が七十七万人前後となると推計された。前年と比べても五.一%減であり、日本の出生率は超低空飛行を続けていると言わざるをえない。
続きを読む
この連載の記事一覧
日本の神々と人と馬の関係性――社会を支え、神を乗せる貴重な存在
かつて、ある神社の宮司さんと談笑していた際、「私はまもなく80歳を迎えるが、例祭ではいまだに装束姿で馬に乗っているんだよ」とおっしゃっていたのを思い出した。この言の通り、各地の神社では時折、祭礼行事にて馬に騎乗した神職らの姿を見ることがある。
続きを読む
この連載の記事一覧
子供たちと向き合って
文部科学省の発表によれば、国公立の小中学校の不登校(三十日以上欠席)の生徒数が二十四万人を突破したそうだ。少子化にもかかわらず九年連続で増加しており、前年度比で二十四.九%増となっている。病欠、別室登校、フリースクール登校の生徒を含めれば、事態はより深刻だ。
続きを読む
この連載の記事一覧
「一食を捧げる運動」に育てられた奨学生が支援の担い手に
戦争の憎しみを乗り越え、懺悔と慰霊が築いてきた対話と交流
立正佼成会の会員がフィリピンを訪問したのは、1973年のことでした。「第1回青年の船」が就航し、約500人の青年部員が渡航先の一つであるフィリピンの地に降り立ったのです。当時はまだ、フィリピン各地に戦争の傷痕が生々しく残っていました。日本軍によって多くの同胞を殺され、社会を破壊され、尊厳を踏みにじられたフィリピンの人々の怒りと哀しみに直面した青年たちは言葉を失ったそうです。そこから、立正佼成会の青年による「慰霊と懺悔(さんげ)」の取り組みが始まりました。
続きを読む
この連載の記事一覧
神紋は個々の神社や御祭神を示すシンボルでもあり、神社の歴史や由緒の一部
小生はいわゆる掃苔家(そうたいか)、“墓マイラー”ではないが、時折、各地の墓苑に赴いて調査を行うことがある。近年の墓苑では、墓石の表面に「〇〇家之墓」といった名称がなく、「倶会一処(くえいっしょ)」といった仏教にちなむ言葉をはじめ、花や楽譜、その人が好んだ文章や四字熟語、あるいは生前の事績が記されるなど、さまざまな形式の墓標が見られる。現代社会における墓は、かつてのような均一的なものでなく、多様な墓の在り方が共存しているのだ。
続きを読む
この連載の記事一覧


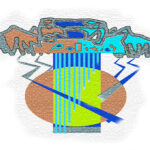
-150x150.jpg)