「時代」の声を伝えて――文学がとらえた80年(15) 文・黒古一夫(文芸評論家)
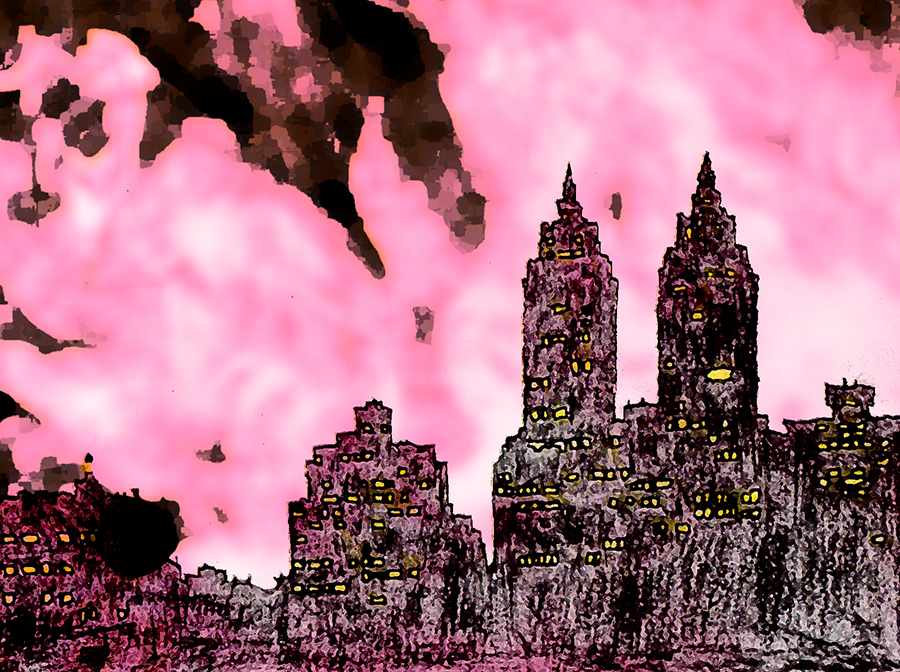
画・吉永 昌生
平穏な日本に迫る「危機」とは
2002年のモスクワ劇場占拠事件、2004年のマドリード列車爆破事件、2005年のロンドン同時多発テロ事件、2009年のムンバイ(旧ボンベイ)同時爆破事件、等々のイスラム過激派やチェチェン独立派によるテロは、世界中に「安全な場所」のないことを証明するものであった。そしてまた、「9.11」はその後のアフガニスタン戦争(2001年)、イラク戦争(2003年)を引き起こし、21世紀もまた「戦争と革命の時代」になるのではないか、と予測させることになった。
「激動」を予感させる世界情勢とは裏腹に、日本は外見的には新世紀になっても前世紀と変わらず「太平の夢」を貪(むさぼ)っているかのようであった。実は、「平和」と見えた日本社会の裏側で、「激動」の世界と連動するように、一つの大きな問題が露頭してきていたにもかかわらず、である。それは、前世紀の終わり頃から問題視されるようになっていたことだが、世界の人口が急激に増加することによって放置することのできなくなった「食料(自給率)」の問題である。
周知のように、日本は戦後復興を工業や商業(情報産業)、サービス業などの第二次・第三次産業を中心にして高度経済成長を果たしたが、食料自給率(カロリーベース)が1960年の79%をピークに大幅に下がり続け、2000年には40%を切るまでになってしまっていた。この低さは、先進工業国の中では例外中の例外で、アメリカ、フランスの100%超を筆頭に、ドイツ90%超、一番低いイギリスでさえ74%で、「異常な事態」になっていた。つまり、私たちが口にする食べ物の60%強が外国からの輸入品であるという現実は、イスラム過激派のテロにおびえる欧米諸国とは違った意味で、日本もまた一種「危機的」な状況にあるということを意味していたのである。






