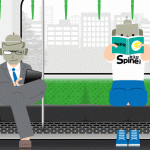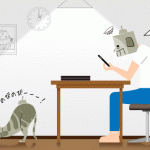小学校の音楽の授業でリコーダーを習い、音楽に楽しさを感じた福井さんは、中学校の吹奏楽部に入り、フルートを吹き始める。しかし、学校には指導者がいなかったため、運指表を頼りに独学で練習を続け、コンクールに出場するまでに上達した。今回は、ファゴットとの出合いや、プロの演奏家を目指すきっかけについて聞いた。
続きを読む
この連載の記事一覧
「ユートピア」を求めて(3)――SF仕立てで「未来社会」を予想
日清戦争(1894・明治27年)に始まって、日露戦争(1904・明治37年)、第一次世界大戦(1914~18・大正3~7年)を経て、満州事変(1931・昭和6年)、日中戦争(1937・昭和12年)、太平洋戦争(1941~45・昭和16~20年)という、50年以上にわたる長い戦争の時代が1945(昭和20)年8月15日に終わる。これによって日本はかつて経験したことのない連合国(アメリカが中心)による「占領」下に置かれるのだが、戦争の苦しみを体験した人々は「平和」と「民主主義」の到来に胸を躍らせることになった。
続きを読む
この連載の記事一覧
日本トップレベルの吹奏楽団として知られる東京佼成ウインドオーケストラ(TKWO)。演奏会をはじめ、ラジオやテレビ出演など、多方面で活躍する。また長年、全日本吹奏楽コンクールの課題曲の参考演奏を行っていることから、特にコンクールを目指す中学生・高校生の憧れの存在でもある。今回は、ファゴット奏者の福井弘康さん。楽器の特徴や、音楽との出合いについて聞いた。
続きを読む
この連載の記事一覧
「体幹を鍛えることで当たり負けない体をつくる」をモットーに、佼成学園高校アメリカンフットボール部「ロータス」の全国大会3連覇に貢献したスポーツトレーナー加瀬剛氏。日頃は、接骨院の院長として、一般の人々のケアにも当たっている。体の構造を知り、毎日をしなやかに過ごすにはどうすればいいか――体の専門家としてアドバイスする。(※ケアの方法を動画で紹介)
続きを読む
この連載の記事一覧
「ユートピア」を求めて(2)
1986年4月26日に当時のソ連(現ウクライナ)のチェルノブイリで起こった原発事故は、国際原子力事象評価尺度(INES)で最も深刻な事故に当たる「レベル7」と認定され、事故発生直後の死者数は「33名」であったといわれている。
続きを読む
この連載の記事一覧
出産によるブランクを乗り越え、ガルシア・安藤真美子さんは今、育児と演奏家の両立を果たし、充実した日々を過ごす。ギタリストの伴侶と新たな音楽活動にも挑戦している。音楽への思い、そして若い人に向けた上達のための練習の秘訣(ひけつ)を紹介する。
続きを読む
この連載の記事一覧
「ユートピア」を求めて(1)
この連載の延長が決まった時、まず考えたのは、戦後73年を10年ごとに区切って「時代」の声を伝えるという趣旨からは外れるが、「戦後社会」という大きな枠組みで捉えた場合、私たちが生きてきたこの社会の現実を相対化する、あるいは問題点を浮き彫りにする作品のことであった。
続きを読む
この連載の記事一覧
TKWOのメンバーになるという中学生の頃からの夢をかなえたガルシア・安藤真美子さん。女性トランペッターで活躍するとともに、一児の母として子育てにも奮闘中だ。数少ない女性トランペッターゆえの葛藤と先駆者としての現在の心境、さらに仕事と家庭の両立を図る出産後の演奏活動について語る。
続きを読む
この連載の記事一覧
日本トップレベルの吹奏楽団として知られる東京佼成ウインドオーケストラ(TKWO)。演奏会をはじめ、ラジオやテレビ出演など、多方面で活躍する。また長年、全日本吹奏楽コンクールの課題曲の参考演奏を行っていることから、特にコンクールを目指す中学生・高校生の憧れの存在でもある。今回は、TKWOでは初めての女性トランペット奏者であるガルシア・安藤真美子さん。トランペットを始めたきっかけや、憧れの存在に出会えたエピソードを聞いた。
続きを読む
この連載の記事一覧
「体幹を鍛えることで当たり負けない体をつくる」をモットーに、佼成学園高校アメリカンフットボール部「ロータス」の全国大会3連覇に貢献したスポーツトレーナー加瀬剛氏。日頃は、接骨院の院長として、一般の人々のケアにも当たっている。体の構造を知り、毎日をしなやかに過ごすにはどうすればいいか――体の専門家としてアドバイスする。(※ケアの方法を動画で紹介)
続きを読む
この連載の記事一覧