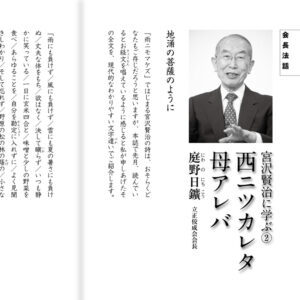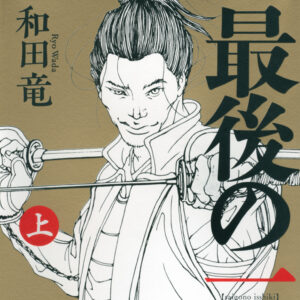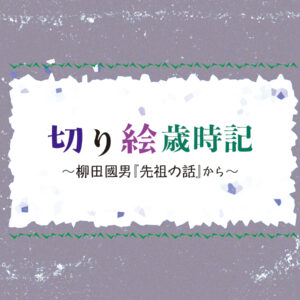新着
「一食を捧げる運動」令和8年度関連活動スケジュールのお知らせ
「一食(いちじき)を捧げる運動」(一食運動)の「中期推進計画」は、『こころがよろこぶ一食』をテーマに掲げて令和6年度にスタートしました。一食運動の提唱から51年目にあたる今年、立正佼成会一食平和基金では主体的・自立的に取り組む一食運動の実践者が増えることを願い、さまざまなイベントやワークショップを計画しています。令和8年度の同運動関連主要活動のスケジュールを紹介します。
トランプ政権の不法移民大量送還に抗議するユニテリアン・ユニバーサリスト(海外通信・バチカン支局)
米国トランプ政権の目玉政策である、不法移民の大量送還。宗教施設内での不法移民の逮捕を禁じた法令を廃棄し、移民・関税執行局(ICE)の職員に強大な権限を与え、施行している。ICE職員は警官ではないが、銃の携帯を許されている。だが、その政策とICE職員による残酷な施行に、同国内の諸宗教者が結束して抗議運動を展開している。
食から見た現代(23) 給食センターで“給食”を食べる子どもたち 文・石井光太(作家)
今年も、文部科学省の国公私立の小中学校に対する調査で、不登校の児童・生徒数が過去最高を更新した。12年連続の増加で、2024年度は小中学校合わせて35万3970人となっている。
内藤麻里子の文芸観察(76)
『のぼうの城』(2007年)、『村上海賊の娘』(2013年)など、寡作ながら出れば話題になる和田竜(りょう)さんの12年ぶりの新作は『最後の一色』上・下巻(小学館)だ。室町時代から200年近く丹後守護を務めてきた一色家の最後を描いた作品だが、こんな戦国小説、読んだことがない。時間をかけて丁寧に構築された世界で武将たちが躍動し、意外性と情け深さに翻弄(ほんろう)される。
切り絵歳時記 ~柳田國男『先祖の話』から~ 2月 文/切り絵 ルポライター・切り絵画家 高橋繁行
人は死ねば子孫の供養や祀(まつ)りをうけて祖霊へと昇華し、山々から家の繁栄を見守り、盆や正月に交流する――柳田國男は膨大な民俗伝承の研究をもとに日本人の霊魂観や死生観を見いだした。戦時下で書かれた柳田國男の名著『先祖の話』をひもときながら、切り絵を使って日本古来の歳時記を絵解きしたい。
バチカンから見た世界(172) 文・宮平宏(本紙バチカン支局長)
-「平和の神学」を説き続けるレオ14世(1)-
米国のカトリック司教会議が、米国とソビエト連邦(現・ロシア)間での冷戦と核戦争への恐怖が頂点に達した世界に向けて、『平和の挑戦——神の約束とわれわれの応え』と題する司牧書簡を公表し、核軍縮や軍拡の停止を訴えたのは1983年のことだった。この司牧書簡は、世界のカトリック教会のみならず、国内外の一般世論にも大きな影響を与え、89年のベルリンの壁崩壊へ向けて道を拓(ひら)くことに貢献した。