利害を超えて現代と向き合う――宗教の役割(67) 文・小林正弥(千葉大学大学院教授)
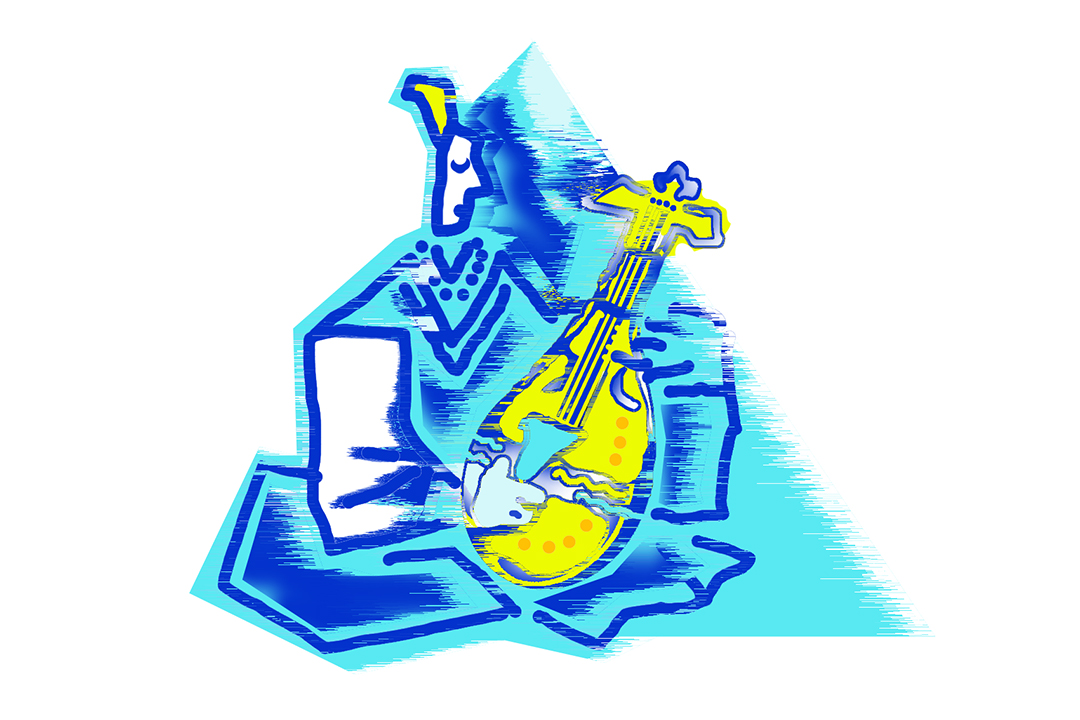
画・国井 節
盛者の「国葬」
「祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹(さらそうじゅ)の花の色、盛者必衰(じょうしゃひっすい)の理(ことわり)をあらはす。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛(たけ)き者も遂(つい)にはほろびぬ、偏(ひとえ)に風の前の塵におなじ」(『平家物語』第一巻)
故安倍晋三元首相の国葬に関して、反対が51.9%、賛成が25.3%と、2倍にもなって(時事世論調査、9月9~12日)、政府は「国葬儀」と言うようになった。自民党は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題に関して「点検」結果を発表したが、不完全で早々に批判を浴びている。内閣支持率も急落して、不支持率が上回り始めた。沖縄では米軍基地問題で政府と対峙(たいじ)している現職知事が選挙で大勝した(9月11日)。
他方で、エリザベス二世女王が崩御され、日本の国葬儀とほぼ同時期に国葬が行われる。そこには世界中の最高レベルの政治家が多数参列する。歴史的に確立している正真正銘の「国葬」と、違憲の「国葬」との品位や性格の相違が、誰の目にも明らかになるだろう。
この国葬について私は平家物語冒頭の文句を思い出す。この国民的文学には、仏教の思想に基づく、日本人の歴史的洞察が凝縮されている。諸行無常は普遍的な真理で、栄枯盛衰が生じる。しかし、栄えた人がすべて同じような速度で衰えて滅びるというわけではなく、その契機となるのは、盛んな者の奢(おご)りなのである。
奢りのもたらす死と必衰
故人の葬儀において語られない問いは、長期政権を誇った故の奢りがなかったかということだ。「桜を見る会」には、往時の平家のごとき、長期政権を寿(ことほ)ぐ華やかさがあり、安倍元首相を囲んだ参加者たちはその感興や、振る舞われた酒食に酔いしれたのかもしれない。
しかし桜の散るのは早い。夙(つと)に酒食の振る舞い方に違法の疑いが生じて、森友・加計学園問題以来の「政治の私物化」が批判された。ところが、権力者はそれを意に介さずに、姿勢を変えなかったように見える。歴代の他の元首相たちだったら、2021年9月に行われた、カルト的宗教である旧統一教会関係のイベントにビデオ・メッセージを送るのは控えたに違いない。あえてそうしたのは、まさに盛者だったがゆえに、自分なら大丈夫と考えたに違いない。
そのメッセージが銃撃犯を刺激して、死を招き寄せてしまった。そして、旧統一教会との密接な関係が露呈して、派閥は動揺している。さらには、「安倍・菅政権」が強行した東京五輪・パラリンピック組織委員会元理事が贈収賄で逮捕され、派閥の長老・森喜朗元首相も参考人聴取を受けた。長期政権下ではさまざまな違法行為や犯罪の隠蔽(いんぺい)や揉(も)み消しの疑いがあったことを考えれば、ここには時流の変化が感じられる。こうして国葬は、「盛者」の真実の姿を直視して議論する国民的な機会になりつつある。これを経て、その「必衰」も現実化するのではないだろうか。
【次ページ:国葬から生まれゆく新しき平家物語?――宗教的叡智と謙虚さの徳】






