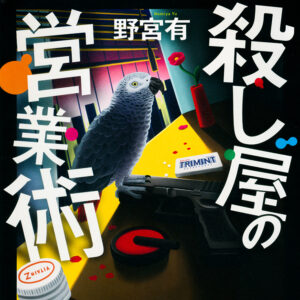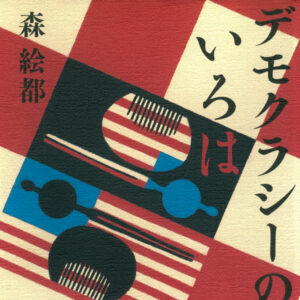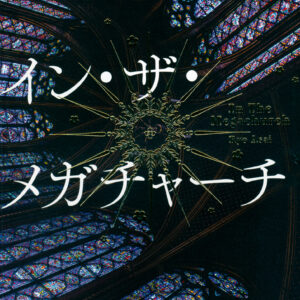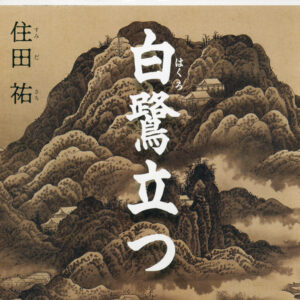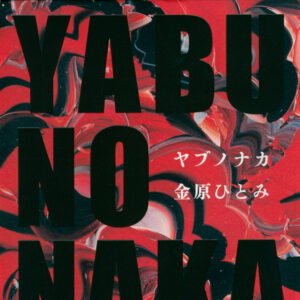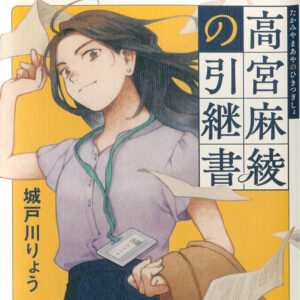内藤麻里子の文芸観察
内藤麻里子の文芸観察(75)
野宮有さんの『殺し屋の営業術』(講談社)は、殺し屋たちが織りなすだまし合いを描いた知的で刺激的な作品だ。コンプライアンスに配慮しなければならない時代に、エンターテインメントに振り切った殺し屋の世界を描き出してみせた。小説とはこういうものだ。
内藤麻里子の文芸観察(74)
森絵都さんの『デモクラシーのいろは』(KADOKAWA)は、敗戦後まもなく、日本人に民主主義を教える“実験”が行われたという設定の物語だ。ドタバタの試行錯誤を活写するコメディーに爆笑しているうちに、自分の足で立つことの意味と希望が胸にしみ入ってくる。
内藤麻里子の文芸観察(73)
“推し活”の世界がとんでもないことになっている。朝井リョウさんの『イン・ザ・メガチャーチ』(日本経済新聞出版)は、推し活を通して現代人の精神のありようを嫌というほど突き付けてくる。その不安、寄る辺なさに打ちのめされる思いがした。
内藤麻里子の文芸観察(72)
住田祐さんの『白鷺(はくろ)立つ』(文藝春秋)は、徹頭徹尾、比叡山の千日回峰行のことしか書かれていない。ところが、これが読ませるのである。物語の持つ磁場に、一気に引き込まれた。
内藤麻里子の文芸観察(71)
優れた業績をあげた女性科学者を顕彰する「猿橋賞」の存在は知っていた。けれど名称に冠された猿橋勝子については何の知識もなかった。伊与原新さんの『翠雨(すいう)の人』(新潮社)は、猿橋の生涯を描いた小説だ。その軌跡は、女性科学者の道を切り開くと同時に、まさに戦後80年の節目である今年、刊行されるにふさわしいものであることに感じ入った。
内藤麻里子の文芸観察(70)
パワハラやセクハラ、SDGs、LGBTQ+に多様性――こうした事柄に対する昨今の意識は、急激に変容している。金原ひとみさんの『YABUNONAKA―ヤブノナカ―』(文藝春秋)は、そんな現代社会で生きる人々の姿を嫌というほど突き付けてくる。読んでいると、とても平静ではいられない。今をどう生きるか問われている。
内藤麻里子の文芸観察(69)
阿部智里さんの『皇后の碧(みどり)』(新潮社)は、これぞ令和に送り出すにふさわしいと言いたくなるようなファンタジー小説である。アニメにもなった和風大河ファンタジー「八咫烏(やたがらす)」シリーズで知られる著者の、新たな挑戦だ。
内藤麻里子の文芸観察(68)
「ブレイクショット」とは、ビリヤードで最初に打つショットのこと。逢坂冬馬さんの『ブレイクショットの軌跡』(早川書房)は、そのショットと同じ名を持つ1台のSUV車が世に放たれ、ビリヤードでボールが飛び散るがごとくあちこちに移動し、それと共に物語が波及していく。現代の闇をさまよう群像が描かれるのだが、もうダメなのかと思った時、かすかな希望が立ち現れる。それはごく簡単なこと、「善良」を取り戻せばいいのだと教えてくれる。静かに胸を打つ会心作と言えよう。
内藤麻里子の文芸観察(67)
いまどきはやりの、キャラクターが立った軽妙なお仕事小説かと思ったら、まったくそんなことはなかった。城戸川(きどかわ)りょうさんの『高宮麻綾(まあや)の引継書』(文藝春秋)は、最初こそ、その雰囲気を漂わせるが、あくの強い主人公が仕事と格闘する姿を描く、かなり本格派のビジネス小説だった。それにポップな衣を着せて、現代が放つビジネス小説と言えよう。うれしい誤算に満ちた快作だ。
内藤麻里子の文芸観察(66)
昨今の小説は派手なアイデアや、特異なキャラクターで読ませる作品が注目されがちだが、平岡陽明さんの『マイ・グレート・ファーザー』(文藝春秋)は、それらとは一線を画す。ファンタジー仕立てであるが、人生の岐路に立った男の姿を静かに、実直に描き、驚くほどじわじわと心にしみてくる。そっと自分の中に取っておきたいような小説だ。