栄福の時代を目指して(13) 文・小林正弥(千葉大学大学院教授)
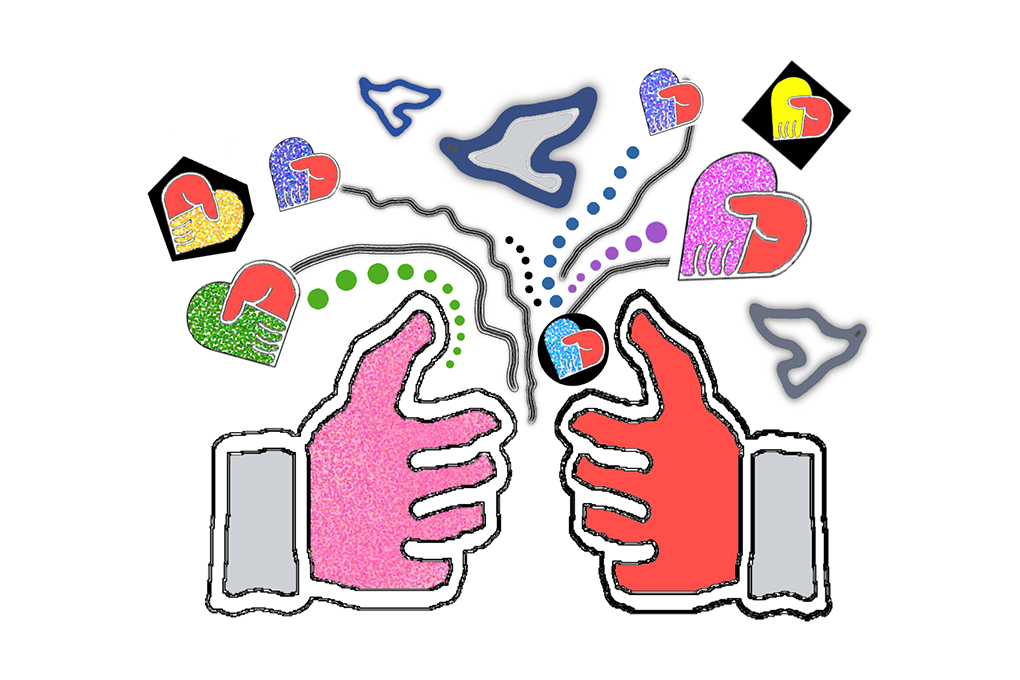
画・国井 節
日本政治の暗転――戦後80年所感の警告
10月21日、高市早苗内閣が発足した。これは、日本政治にとって極めて深刻な歴史的事件になり得るので、今回は日本政治に絞って論じよう。
石破茂首相は「石破おろし」にもかかわらず、世論の支持に支えられて健闘し、8月には原爆や終戦の記念日で貴重な式辞を述べたが(第11回〈前編〉参照)、抗しきれずに遂に辞任を表明した。10月4日に自民党は反石破の高市早苗氏を総裁に選出したが、高市氏は安倍路線の継承を掲げており、極右的な政治路線の主張者だ。こうして、日本政治は暗転した。
実際に、石破おろしを主導した麻生派から、副総裁と幹事長を選び、幹事長代行を旧安倍派5人衆から選ぶという布陣が報道された。高市氏は、いわゆる裏金議員の要職起用について聞かれると、「党の処分や選挙で審判を受けている。適材適所で力を発揮してほしい」などと、平然と嘯(うそぶ)いていた。事実、内閣では旧安倍派の裏金議員を7人も副大臣・政務官に任命したのである。
要は、石破政権下では斥(しりぞ)けられていた安倍政治が亡霊のように復活することになるわけだ。裏金問題や物価高などで自民党は、参院選挙で敗北したにもかかわらず、その責任を石破首相に負わせて退陣させ、これらの問題に加担した重鎮たちが新政権の枢軸をなすわけである。初の女性首相ともてはやす声があるが、人々の生活に多大な影響を及ぼす首相については、重責に鑑みて、男女の性ではなく政策内容で善悪を判断しなければならない。平和や民主主義という政治の理想に関しては暗澹(あんたん)たるものだ。
10月10日、石破首相は戦後80年所感を発表し、戦後の代表的な政治学者・丸山眞男の言葉も援用しつつ、文民統制の不在、斎藤隆夫衆院議員の反軍演説、組織の割拠制の問題などに言及し、政府・議会やメディアなどの政治システムが大戦突入を回避できなかった理由を総括した。「今日への教訓」として、「無責任なポピュリズムに屈しない、大勢に流されない政治家としての矜持(きょうじ)と責任感を持たなければなりません」「偏狭なナショナリズム、差別や排外主義を許してはなりません」と述べて、「過去を直視する勇気と誠実さ、他者の主張にも謙虚に耳を傾ける寛容さを持った本来のリベラリズム、健全で強靱(きょうじん)な民主主義が何よりも大切です」とした。
これらは、まさに高市氏の「偏狭なナショナリズム」や参政党などの「無責任なポピュリズム」と「差別や排外主義」を想起させる。あたかも、これらの危険に対して、石破首相が「最後の言葉」として警告と戒めを公共的に発したかのようだった。
政治的大激変――公明党の連立離脱と連合政権期の到来
少数与党から脱却するために、高市氏は国民民主党に連携を打診したが、公明党が、自民党は企業団体・献金の規制強化などで明確な姿勢を示していないという理由で、連立政権離脱を決めた。石破首相退陣後に斉藤鉄夫代表は「保守中道路線でなければ、連立を組むわけにはいかない」(10月14日)と述べていたから、この言葉通りの決定を行ったわけだ。ところが、この言葉を本気に受け取っていなかった自民党は、大混乱に陥った。1999年から(非自民党政権の3年も含めて)26年間も続いた自公連携が終焉(しゅうえん)することになり、日本政治の景色はまったく変わることになった。
1955年からの自民党中心の政権の体制は、民主党政権などで中断したが、2012年以降は自公連合によって復活している。学問的には「一党優位政党制」(ジョヴァンニ・サルトーリ)という。ところが、自公連合が崩壊したので、この体制が終わり、自民党は他の野党と連合せざるを得なくなる。いわゆる「連合政権の政治」に入るわけだ。
故・篠原一先生(東京大学名誉教授、ヨーロッパ政治史)が、ヨーロッパの連合政権の政治を研究して、いちはやく提唱していた政治方式である。その謦咳(けいがい)に親しく接する幸運に恵まれたことを思い出す。提唱された「歴史政治学」の影響で、私は初めの研究テーマ(政治的クライエンテリズム)を決めたのである。
同時に、参議院選挙によって、自民党よりも右の極右政党(参政党、日本保守党)が明確に出現したので、左の共産党、社会民主党から極右まで政党が左右に大きく分かれることになった。私たちの参議院選挙分析でも、各政党の支持者に政策を尋ねたところ、左右軸が明確に析出された。つまり、有権者は基本的に左右軸に即して、政党支持を行っていることがわかる。
多数の政党が左右に大きく分かれると、政治が不安定になりやすい。一時期のイタリアがこのような政治となっていた。学問的には、分極的多党制という。現在の日本の場合、かつての社共(社会党・共産党)に比べて、共産党が立憲民主党などと選挙協力をするなどのように穏健化しているし、左翼政党の党勢が衰えているので、そこまではなっていない。それでも、幾つかの政党が政権構成に影響をもたらすという点で、多党制の状況に入りつつあるように思われる。
「80年所感」が警告した通りの極右連合――中道連合への動向
国民民主党は、公明党抜きでは多数派にならないので連立に否定的なコメントを出した。そこで、高市氏は日本維新の会に打診し、日本維新の会は、突然、国会議員の定数削減を強く要求した。そして12の政策テーマに合意がなされて、この政党の閣外協力によって内閣が発足した。合意書には、企業団体献金については曖昧(あいまい)になった反面で、定数削減や副首都構想とともに、安保関連3文書の改定や、憲法改正、皇室典範改正、スパイ防止法制定、外国人政策などが並び、極めて右派色が強い。
日本維新の会は、民営化・規制緩和・自己責任論などの主張が強いという点でネオ・リベラリズム(リバタリアニズム)中心の政党だ。この思想の政党は、右派色の強いことが多いので、自民党と連携することは不思議ではない。実際、私たちの調査でも、支持者の政策支持において、公明党の次に自民党に近いのは、日本維新の会だった。
そして、「NHKから国民を守る党」の国会議員とともに、自民党は参議院で統一会派を組むことにした。この党は、極端なポピュリズム政党であり、元代表については有罪が確定したり行為の違法性が疑われたりしているほどだから、驚くほかない。良識と品位ある人士なら、眉をしかめるに相違ない。さらに高市氏は参政党にも「参政党とは政策が近い」と述べて、首相指名の協力を要請した(16日)。参政党は首相指名選挙で高市氏に投票はしなかったが、自民・維新・参政・NHK党となれば、明らかな右派連合となる。特に、高市総裁と参政党が極右なので、もし参政党が加われば、極右連合の色彩が濃くなるところだった。
つまり、石破首相が戦後80年所感で警告した「ポピュリズム」と「偏狭なナショナリズム」と「差別と排他主義」が、後継の政権では結びつきつつあるわけだ。所感は、大戦を再び引き起こさないことを願って述べられたものだから、これらが結合して次期政権を誕生させるということは、戦争の危険が迫ると石破首相が言っているも同然だ。
このような右派連合が政権を獲得するのは、平和や民主主義にとって極めて深刻な事態だ。トランプ政権を考えてみてもわかるだろう。そもそも、自公政権では、公明党は自民党に協力しつつ、一定のブレーキもかけていた。その牽制(けんせい)がなくなり、安倍政治が復活して思うままの政治を行うようになれば、日本の将来に暗雲が立ち込めると憂うるしかない。良識派の村上誠一郎前総務省は、退任の挨拶で、幹部職員たちに、世界情勢や日本のポピュリズム勃興に言及して「民主主義が危ない」と涙声で説いた(22日)が、正しい認識に基づく至誠の訴えで、胸を打たれる。一人でも多くの人々が、80年所感が暗示している危険に気づくことを願って止まない。
他方で、野党側は、立憲民主党の幹事長が、公明党の連立離脱が報じられるとすぐに各党に連立の呼びかけをして、当初は国民民主党・玉木雄一郎代表が首相となる可能性も挙げていた。さらに、公明党が野党に加わる意思を示したので、公明党とも連携の協議を試みた。
公明党は、平和・福祉や「クリーンな政治(清潔政治)」という理念を掲げていた。その政党が自民党と長年、連立して、安保法制なども含めて協力してきたのだから、立党の理念と明確に反していた。しかし、裏金問題の中心だった自民党安倍派議員たちが政権要職に就くことになり、多くの議員や支持者が、元来の理念との乖離(かいり)に堪えきれなくなったのだろう。そこで、要求していた政治資金改革も行う意思がないことを確認して、連立から離脱したのだろうと推定される。自公連立を継続してきた代表たちも交代しており、現在の斉藤代表が理念に即した決定を行ったのは、政党の理念という本義に即していて、高く評価できる。今後は、平和・福祉に加えて、政治腐敗問題に対して倫理的政治の復活に向けて働きかけることを期待したい。
倫理的中道の可能性――徳義共生主義の時代を
立憲民主党は現在、「中道ど真ん中」(野田佳彦代表、4日)という立ち位置を主張しているから、公明党との連携は、政策という観点から、中道政治の推進という点で合理的だ。さて、ここで生まれる重要な政治的可能性がある。
国民の多くが、政治腐敗問題によって与党を信頼できなくなり、参議院選挙でも与党が大敗したにもかかわらず、立憲民主党の議席が伸びなかったのは、この政党がリベラリズム中心だったからだろう。
私は「リベラリズム」と「自由主義」をカタカナと漢字で分けて表記している。後者は、近代革命によって自由と権利を確立してきた貴重な政治思潮であるのに対し、前者は(アメリカなどの政治哲学の影響を受けて)「善い生き方」に関する倫理的な主張を避けて、法律や手続きの主張に特化するという点で、非倫理的な思想だからである。政治腐敗問題は法律違反でもあるが、何よりも道義的な問題だ。だから、倫理的批判を行わなければ、人々に訴える力は弱い。
他にもリベラリズムはさまざまな問題点を持っている。たとえば、個人中心の反面、家族や国民などのコミュニティーの主張はあまり行わない。この弱点を突いたのが、「日本人ファースト」という参政党などの極右ポピュリズムだ。実際、今の日本では、人口減少のように、「コミュニティー」問題が最大の要になってきている。このため、この種の問題を回避するリベラリズム政党は、自民党に愛想を尽かした多くの人々の期待を集めることが難しいのである。
よって、今の日本に必要なのは、倫理的な中道政治であり、コミュニタリアニズム(徳義共生主義)に基づく政治である。立憲民主党と公明党との連携が進めば、宗教的政党が加わることによって、全体としては自ずと倫理的な中道の可能性が浮上するだろう。
もちろん、これだけでは必ずしも十分ではない。他の政党も含めて政党間の連合が進展し、その中から、本格的な徳義共生主義が政治において現れていくことが必要だ。もしそのための契機になれば、今回の政治的激変にポジティブな意味が生じてくる。
倫理的な政治を待望している人は、他の多くの宗教的・倫理的な人々にも多いはずだ。そういった人々の声が集まり、この二つの政党に留まらず、政治的・倫理的な政治の潮流が、現在進行中の政治的激変から新しく始まっていくことを期待したい。
冒頭に述べたように、現在進行中の重大事態に注意を喚起するため、今回は即礼君の物語はお休みにする。今は、巨大な暗雲と希望がともに現れ、交錯している。次の国政選挙では、公明党の選挙協力なしには自民党の得票数は減ると予想されるから、この帰趨(きすう)はまだ定まっていない。絶望するのはまだ早い。人々がこの事態を理性的に見抜き判断できるかどうかに、日本の命運がかかっているのである。
プロフィル

こばやし・まさや 1963年、東京生まれ。東京大学法学部卒。千葉大学大学院社会科学研究院長、千葉大学公共研究センター長で、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特別招聘(しょうへい)教授兼任。専門は公共哲学、政治哲学、比較政治。2010年に放送されたNHK「ハーバード白熱教室」の解説を務め、日本での「対話型講義」の第一人者として知られる。日本ポジティブサイコロジー医学会理事でもあり、ポジティブ心理学に関しては、公共哲学と心理学との学際的な研究が国際的な反響を呼んでいる。著書に『サンデルの政治哲学』(平凡社新書)、『アリストテレスの人生相談』(講談社)、『神社と政治』(角川新書)、『武器となる思想』(光文社新書)、『ポジティブ心理学――科学的メンタル・ウェルネス入門』(講談社)など。






