利害を超えて現代と向き合う――宗教の役割(90)最終回 文・小林正弥(千葉大学大学院教授)
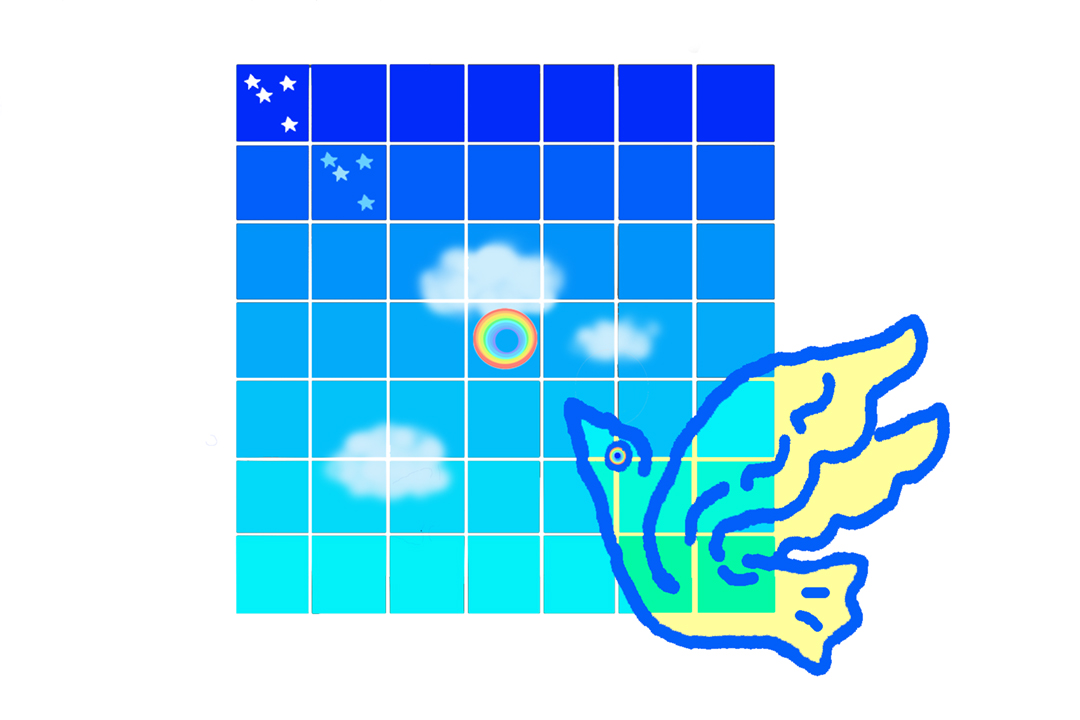
画・国井 節
四十九日と死後の審判
四十九日は故人を偲(しの)びつつ、その冥福を祈る期間である。宗教的発想ではたいてい、この世を超えた超越的世界があり、死者の魂は現世からその世界へと移行すると考えられている。日本の仏教や民間信仰では、この期間に死者たちは「中有(ちゅうう、中陰ともいう)」という状態にあり、冥土の旅をしていて、「十王」という10人の裁判官の審判を受けるとされている。“初七日”後の最初の裁判から始まって、七日ごとに七回裁判があり、14日目に三途(さんず)の川を渡る。その後、35日目には閻魔(えんま)大王の裁判があり、“四十九日”に最後の裁判が行われて、生前の行いに応じて極楽や地獄に行くとされている。いわゆる成仏のためのものだ。この成仏のために法要や供養、祈りに意味があるとされており、だからこそ、この期間は死者のための集中的な祈りの期間でもある。※第68回:葬儀における宗教的意味
我が家では、娘がこの裁判について妙に詳しく知っていたので不思議に思って聞くと、『キャラ絵で学ぶ! 地獄図鑑』(すばる舎)という絵本がその理由だった。子どもの興味を引くように作られている絵本なのだが、手に取ってみると、浄土宗の祖とされる源信(942~1017)の『往生要集』に依拠しており、有名な宗教学者・山折哲雄氏が監修していた。『往生要集』は当時のいわばベストセラーであり、叫喚(きょうかん)地獄や焦熱地獄、阿鼻(あび)地獄などの八大地獄と極楽浄土が事細かく活写されていて、日本仏教の極楽・地獄の観念に大きな影響を与えた歴史的作品である。こうして私たち大人よりも子どもが詳しい知識を持っていた謎が解けた。おそらく怖い物見たさで買う子どもが多い絵本にも、想像以上の意義があることがあるものだと思って、苦笑してしまった。
死者の追憶と、死を意識した生――四十九日の哲学的意義
さて、死後の裁判とは違って、この世界における故人の追憶は、問題点や短所よりも、その人の素晴らしかった点や長所に向かうことが多いものだ。先月に亡くなった父の回想も、主としてその仕事の意義や恩、感謝へと向かった。特に一緒に過ごした時の記憶が甦(よみがえ)り、その頃の自分をも思い出した。私の場合、30歳ごろに実家を離れたから、約30年ぶりに当時の意識が呼び覚まされたのである。
同時に、死に意識を向けるということは、翻って将来における自らの死や残りの人生へと思いを向かわせる。亡くなった父との年齢差が約30歳あるから、仮に没年齢までの生を三つに分けると、私はこれからが第3期、その終点に己の死が存在することになる。この自覚は、自(おの)ずとこれまでの自らの人生の回顧と、残りの生き方への再考へと向かった。
20世紀ドイツの有名な哲学者マルティン・ハイデッガーは、自らの死の可能性を引き受けながら生きることを「死への先駆」と呼び、それによって非本来的な生き方から本来的な生き方へと転換することができると考えた。これは、哲学関係の講演で時に言及することだが、父の死により私の思念は期せずして、「本来の生」へと向かうことになった。
多くの人々は、忙しい日常生活では、繁忙に紛れて死を意識することは少なくなりがちであり、本来の生き方を貫徹することは難しい。ところが、四十九日のような期間が文化的・社会的に設けられていて、忌中には外出や祝い事、旅行などをなるべく控えるという慣習がある。これは、死の穢(けが)れを他人に伝染(うつ)させないという宗教的な理由に基づく。
この期間に、自分の「本来の生」について思索し生き方を静かに省察することが可能だ。こうすることによって、四十九日に宗教的意義とともに哲学的・実存的な意義も生じさせることができるだろう。
【次ページ:人間を幸福にする学問は何か――経済と政治と哲学】






