栄福の時代を目指して(10) 文・小林正弥(千葉大学大学院教授)
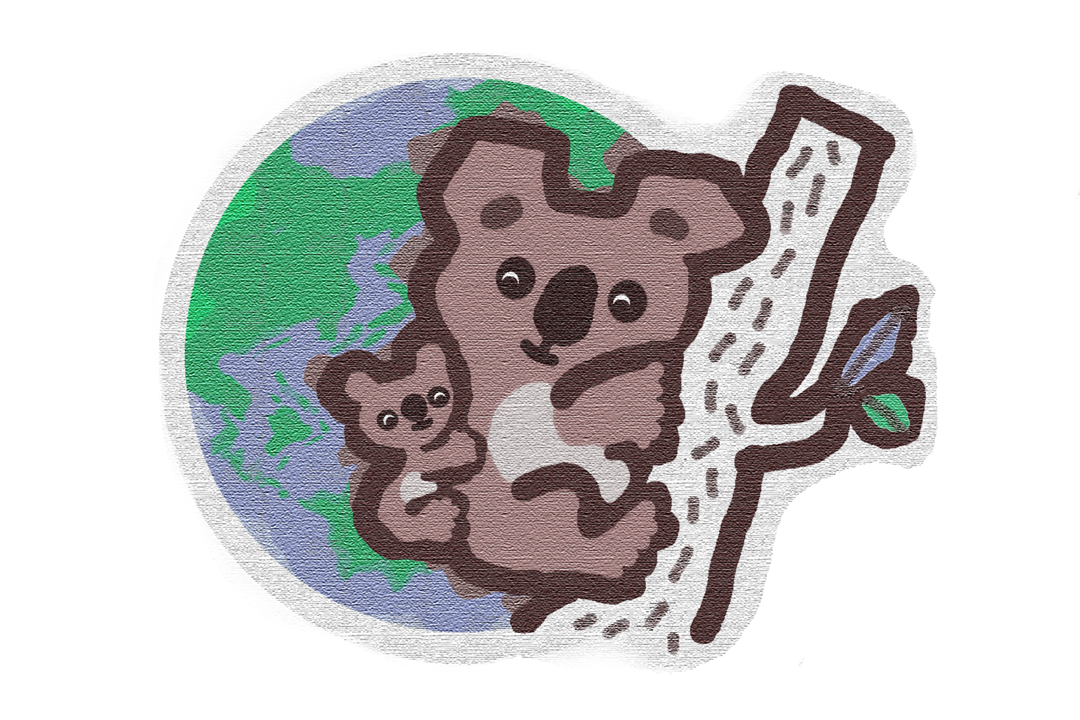
画・国井 節
平和なコアラと戦火――禍中の世界に灯り続ける「栄福」への希望
イスラエルとイランの停戦はなんとか維持され、12日間戦争が終結した。すぐに世界大戦へと進む最悪のシナリオは幸い回避されたのである。
しかしイスラエルはガザにおける攻撃を続けており、今度はシリアの首都ダマスカスの暫定政府軍本部などを空爆した。少数派(ドゥルーズ派)の保護を名目にしているが、国際法違反という批判や懸念の声が安全保障理事会でも相次いだ。ガザの大虐殺(ジェノサイド)などでイスラエルを非難する国際的な声は、イラン先制攻撃を支持した欧州にすら広がりつつあり、スペインや中国などが国際法上の犯罪に対する処罰を(正当にも)主張している。だが、この攻撃を阻止する有効な手段は国際的にとられておらず、戦火が燃え盛る事態は続いている。
世界の戦禍や苦悩を背景として、国際ポジティブ心理学会の第9回世界大会が、オーストラリアのブリスベンで7月2日~5日にかけて開催され、私は渡航して発表(口頭発表3、他の先生方が中心となるポスター発表3)をした。三つの口頭発表では、万学の祖と言われるアリストテレスなどの古典哲学を念頭に、正義や公正(の認識や志向性)がコロナ禍における健康悪化・格差や、政治の価値に対する認識に影響していることや、美徳の倫理(特に中庸思想)を実証的に明らかにした(ⅰ)。一つのセッションでは司会に選出され、英語での司会は初めてだったので、新しいチャレンジでもあったが、出会いも多く、とても充実した経験となった。
この会場では、オーストラリアを代表する動物のコアラが展示されていた。さらに、私は本大会開催前の時間を活用して、開催地近辺にある、コアラ中心の動物園(コアラ・サンクチュアリー)に車を駆って訪れ、間近で観ることができた。動物園の各区画では、樹上のコアラがユーカリの葉を食べていたり、枝の上で寝ていたりして、とても愛らしかった。ゆったりした平和な雰囲気は、疲れた心を慰め癒やしてくれる。
国際ポジティブ心理学会の世界大会は2年に一度、開催国を変えて開かれており、私は2015年(第4回世界大会)から連続して参加して、世界におけるポジティブ心理学の生き生きした展開とその活発なエネルギーを体感し、最先端の動向を『ポジティブ心理学』(講談社選書メチエ、2021年)などで日本に紹介してきた。ポジティブ心理学の内容を反映して、通常の学会とは趣が異なり、研究者とともに、医師やカウンセラー、ワークショップのファシリテーター、コーチなどのプラクティショナー(実践者、施術者など)も数多く参加している。ポジティブな温かい雰囲気に包まれて、雄弁なスピーチも多く、さまざまな感動や出会い、再会、興奮の渦が生じるのである。研究成果を分かち合うとともに、ポジティブな変化を引き起こす人に対する賞(ジェームズ・ポウェルスキ ポジティブ・カタリスト賞)があるように、世界や人々にポジティブな変革を促すことも、この世界大会の目的の一つなのである。
しかし、コロナ禍が始まって2021年の世界大会はオンライン開催となり、私も発表したものの、通常開催に戻った2年前は参加できなかったので、6年ぶりの対面参加だった。この間、私は海外に行くことができなかったので、渡航自体が久しぶりである。
この連載のタイトル『栄福の時代を目指して』における「栄福」は、この学問の創始者マーティン・セリグマンが「幸福」に代わって用い始めた「flourish(フラーリッシュ)」という概念の訳語として考えたものだ。もちろんセリグマン自身もコロナ禍前にはこの世界大会に毎回参加しており、これを通じて彼も含めた学会の中心の方々と私は知己となった。
初めてポジティブ心理学に関心を持った頃に、セリグマンのいるペンシルバニア大学を尋ねて、ポジティブ心理学センターで教育ディレクター(ジェームズ・ポウェルスキ博士)とお会いしてお話しを伺った。博士は哲学の研究から出発してポジティブ心理学の実践的展開を牽引(けんいん)しているために、私にとって“導きの糸”そのものとなり、世界大会の事務局長でもあったので、参加を勧められたのである。
ポジティブ心理学は、個人のウェルビーイング(幸福感)を中心に研究しており、当初は「政治哲学とポジティブ心理学を架橋する」という私自身の問題意識が有意義かどうかわからなかったので、中心の方々に尋ねた。セリグマンは、この点について話した時にはいつも、アリストテレスの「高貴な学としての政治学」に言及し、政治をはじめ社会科学とポジティブ心理学を結びつける必要性に深い理解を示して、それを推進するリーダーが必要だ、と言って激励してくださった。他にも、同様に温かく激励してくださった先生方は数多い(ポジティブ組織学の主導者キム・キャメロンや、今回の大会で受賞した心理学の泰斗のキャロル・リフなど)。それらに鼓舞されて、2015年の初参加の時(於 アメリカ・フロリダ)からは毎回、口頭発表を行ってきた。特に、2019年の第6回世界大会(於 オーストラリア・メルボルン)では、セリグマンの推薦により口頭発表のセッションを作って頂き、ポジティブ政治心理学という新概念を提起した。
この間、名前を挙げた先生方も、それぞれの形でこの世界大会で、マクロな問題や、社会経済問題などに取り組む必要性に言及されておられたし、こういった方向を提唱する流れも生じてきた(ポジティブ心理学3.0やシステム論的ポジティブ心理学など)。久しぶりにこの世界大会に参加したので、最新の動向も知りたいと思っていたのだが、今回、中心人物の1人(ポジティブ感情の研究で有名なバーバラ・フレドリクソン)をはじめ何人もの先生方が、今年もっとも印象に残っているなどと述べられたのが、「再生成的ポジティブ心理学――私たちの世界の現実に応えるためのウェルビーイング科学再方向設定への訴え」という論文だった(ⅱ)。
これは、ポジティブ心理学の旗艦誌『ポジティブ心理学ジャーナル』で今年掲載されたものであり、私たちのウェルビーイングにとって必要な生命維持のシステムの成長や健康を守り、拡大するために、この学問の方向を再設定することを提案している。このために、個人のウェルビーイングへの過度の強調を再評価して三つの柱を提起し、世界の危機を直視して、全ての人々の、よりポジティブな未来を建設するためのリーダーシップを取るという理想を示している(ⅲ)。「人生の意味」に関する研究で有名な執筆者(マイケル・スティーガー)も、大会の最後の全体セッションで力強く講演をされて、持続可能性などの問題を示して、ポジティブ心理学がこれらの問題に取り組み、再生する必要性を訴えられた。これは、私自身の追求している方向そのものなので感銘を受けたことは言うまでもない。改めてこの方向に寄与することを心に期した次第である。
でも、このような必要性が自覚されて訴えられた背景には、今日の世界的危機があると思われる。全体講演では、グローバル平和やポジティブ平和についての講演(エレナ・マルジョ)もあり、私自身も使っている概念なので共感した。そして何よりも、オンラインセッションで質問に答えたセリグマンは、戦争や紛争について尋ねられ、部族的心理に言及したが、今後のビジョンについては、かねてから提示している「PERMA51」について改めて述べた。これは、2051年までに世界の51%の人々が栄福を実現する、というポジティブ心理学の長期的使命だ(マーティン・セリグマン『ポジティブ心理学の挑戦』、ディスカヴァー・トゥエンティワン)。
「フラーリッシュ=栄福の時代」の到来というこの連載のビジョンも、これに触発されている。その意味ではこの考え方は私には馴染み深いものだが、イスラエル・イランの12日間戦争の余燼(よじん)がくすぶり続けているこの時期に、不動のビジョンを語る姿には、改めて希望を感じた。今は、2025年であり、21世紀に入って四半世紀が過ぎた。しかし、2051年までにはまだ26年、もう四半世紀がある。いかに世界史の逆流が生じていようとも、希望を捨てるのはまだ早い。このビジョンに向けて、孜々(しし)と歩んでいくことがポジティブ心理学の役割だろう。
暗い世相は、世界大会の運営にすら影を落としていた。いつも大会の最後には次の開催地が発表され、またそこで多くの人々と出会うことを呼びかけて終了するのだが、それはなかった。代わりに、次の会長(精神科医タイーブ・ラシッド)が、地政学上の理由を挙げて、多くの人々の意見を聞いて決めると述べた。現に私も大会の間に、トランプ政権の政策により、入国者のSNSを調べてアメリカ批判者に対する入国を拒否することが起こっていることを念頭に、アメリカが次の開催地となると参加が難しくなりかねないという懸念を要人たちに伝えたのである。
自由の国だったアメリカで国際学会開催に支障が生じるというような事態は、数年前には想像もできなかった。振り返ってみれば、コロナ禍から始まって開催自体に及ぶような問題が次々と生じていることになる。これ自体が、世界の危機と混乱の連続的進行を象徴的に示している。
ここには巨大なコントラストを観取(かんしゅ)できる。栄福を研究しその時代の到来を目指す学問的世界大会と、感染症や戦争との対照――平和なコアラの姿と、多くの死や流血とのコントラストである。しかし、この危機と混乱の時代の先には、平和と繁栄・幸福の時代が待っていること、あるいはそのポジティブな世界を私たちは自分たちの努力によって開拓できるということを信じて、即礼君の物語に戻ろう。
(ⅰ)結論は次の通りである。①心身の状態(ウェルビーイング)は密接に関連しており、コロナ禍において、社会における正義・公正の存在を人々が感じていると認識していると、心身の健康悪化が食い止められて、健康に関する格差が小さくなる傾向がある、②正義の美徳と人格的強みとの関係を分析したところ、人々がこれらを持っていると、政治に関する価値観が正義・公正や腐敗反対の方向に向かう傾向がある、③アリストテレスの中庸という思想について、独自の調査票を作って分析して、その思想の正しさを明らかにし、実証的には、真ん中よりやや多めに美徳を持っていると感じる人がもっとも幸福になる傾向がある
(ⅱ)Michael F.Steger,“Regenerating positive psychology: A call to reorient well-being science to meet the realities of our world,” The Journal of Positive Psychology, 2025, vol.20, n.3, 373-396.
(ⅲ)この三つの柱とは、「①ウェルビーイングの定義の拡大(個人から、個人を含んだシステムへ)、②ウェルビーイングのシステム科学の建設、③ポジティブな人間のケア(ケアテーキング:配慮・世話など)のための知識生成」である。






