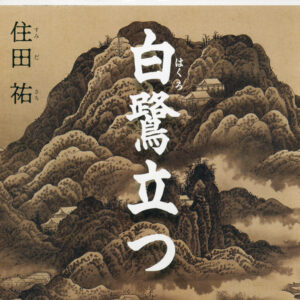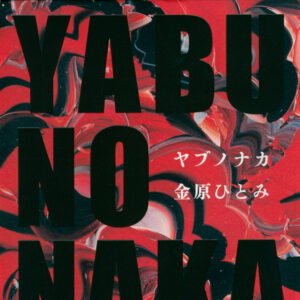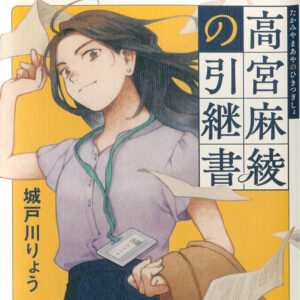壮年部の活動 幸せに向かう道を仲間と歩む
コロナ禍を経て、壮年部活動が新たに始動している。教会の枠を超えた交流法座や練成会、青少年活動の陰役……。壮年部のさまざまな活動は、自らの信仰を見つめ、奉仕の喜びを味わい、法友とのつながりを実感する場だ。このほど行われた、千葉、多摩両支教区の活動を通して、壮年たちの“現在(いま)”を紹介する。
内藤麻里子の文芸観察(72)
住田祐さんの『白鷺(はくろ)立つ』(文藝春秋)は、徹頭徹尾、比叡山の千日回峰行のことしか書かれていない。ところが、これが読ませるのである。物語の持つ磁場に、一気に引き込まれた。
フレンドシップタワー 50周年式典を開催 「加害」を知り、傷ついた先に見た平和(動画あり)
7641もの美しい島々が連なる群島国家・フィリピン。その中の一つ、ルソン島の南西部に位置し、マニラ湾と南シナ海に挟まれた半島がある。バターン半島だ。ここは第二次世界大戦中、旧日本軍が捕虜を収容所まで歩かせた「死の行進」が行われた場所である。戦争の傷痕が深い地に、日比友好のシンボルであるフレンドシップタワーが建立され、今年で半世紀となる。4月5日~10日、庭野光祥次代会長を名誉団長とした「フレンドシップタワー50周年特使団」(一行48人)がフィリピンを訪れ、平和への祈りを捧げる旅に出た。
内藤麻里子の文芸観察(71)
優れた業績をあげた女性科学者を顕彰する「猿橋賞」の存在は知っていた。けれど名称に冠された猿橋勝子については何の知識もなかった。伊与原新さんの『翠雨(すいう)の人』(新潮社)は、猿橋の生涯を描いた小説だ。その軌跡は、女性科学者の道を切り開くと同時に、まさに戦後80年の節目である今年、刊行されるにふさわしいものであることに感じ入った。
内藤麻里子の文芸観察(70)
パワハラやセクハラ、SDGs、LGBTQ+に多様性――こうした事柄に対する昨今の意識は、急激に変容している。金原ひとみさんの『YABUNONAKA―ヤブノナカ―』(文藝春秋)は、そんな現代社会で生きる人々の姿を嫌というほど突き付けてくる。読んでいると、とても平静ではいられない。今をどう生きるか問われている。
福岡教会 街頭募金でミャンマーの人々の安寧を祈る
初夏の風が福岡市の繁華街を吹き渡る中、「募金お願いします!」という力強い声が響いた。立正佼成会福岡教会は5月18日の午後、「青年の日」の取り組みとして、青年部員ら120人が、博多、天神、大橋の3カ所に分かれて、世界宗教者平和会議(WCRP/RfP)日本委員会による「ミャンマー地震緊急支援募金」への協力を呼びかけた。
内藤麻里子の文芸観察(69)
阿部智里さんの『皇后の碧(みどり)』(新潮社)は、これぞ令和に送り出すにふさわしいと言いたくなるようなファンタジー小説である。アニメにもなった和風大河ファンタジー「八咫烏(やたがらす)」シリーズで知られる著者の、新たな挑戦だ。
内藤麻里子の文芸観察(68)
「ブレイクショット」とは、ビリヤードで最初に打つショットのこと。逢坂冬馬さんの『ブレイクショットの軌跡』(早川書房)は、そのショットと同じ名を持つ1台のSUV車が世に放たれ、ビリヤードでボールが飛び散るがごとくあちこちに移動し、それと共に物語が波及していく。現代の闇をさまよう群像が描かれるのだが、もうダメなのかと思った時、かすかな希望が立ち現れる。それはごく簡単なこと、「善良」を取り戻せばいいのだと教えてくれる。静かに胸を打つ会心作と言えよう。
全国新任サンガデザインを実施 自他の尊厳を守る大切さを学ぶ
令和7年次「全国新任サンガデザイン(旧全国新任青年各部長教育)」(青年ネットワークグループ主管)が2月23日、『私の弱さをデザインする』をテーマにオンラインで行われた。今年度に新たに役を拝命した青年ら65人が参加した。
内藤麻里子の文芸観察(67)
いまどきはやりの、キャラクターが立った軽妙なお仕事小説かと思ったら、まったくそんなことはなかった。城戸川(きどかわ)りょうさんの『高宮麻綾(まあや)の引継書』(文藝春秋)は、最初こそ、その雰囲気を漂わせるが、あくの強い主人公が仕事と格闘する姿を描く、かなり本格派のビジネス小説だった。それにポップな衣を着せて、現代が放つビジネス小説と言えよう。うれしい誤算に満ちた快作だ。