内藤麻里子の文芸観察(4)
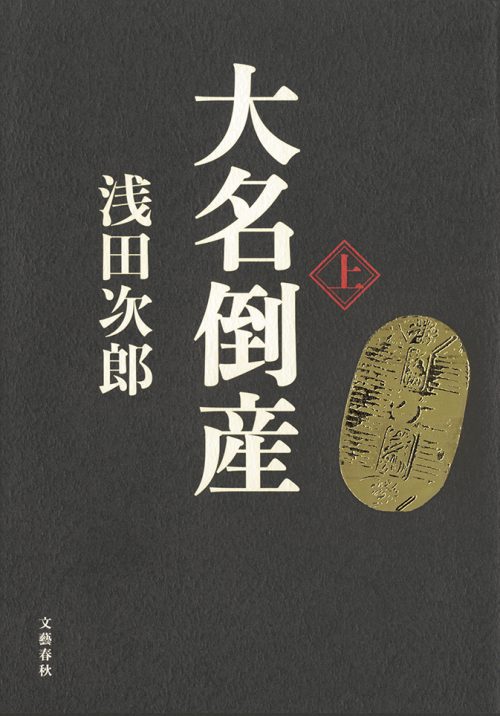
泣ける小説の名手と言って、まず思い浮かぶのは浅田次郎さんであるが、この作家はまた笑える小説の名手でもある。
『プリズンホテル』(1993年)、『オー・マイ・ガアッ!』(2001年)などのコメディーと比べても、新作の『大名倒産』上・下巻(文藝春秋)は、思い切り“お笑い”に振り切っている。しかも、時代小説でこれをやってのけた怪作である。参勤交代を描いた『一路』(2013年)とはガラリと趣向を変え、最近注目される武家の内実やお金の苦労がモチーフである。
時は幕末。越後丹生山(にぶやま)三万石を継いだ松平和泉守信房は、先代が村娘に手を付けて生まれた四男。思いがけず後継ぎのお鉢が回ってきた。
御殿様になったのはいいけれど、ふたを開けてみれば御家は火の車。隠居した先代は、大名倒産をもくろみ、詰め腹を切らせるつもりで四男を当主にしたのだ。何も知らない和泉守は藩の立て直しに躍起になる。隠居対和泉守、軍配はどちらに上がるか。ここに、水売りやら山賊、貧乏神に七福神まで絡むドタバタ劇の幕が切って落とされた――。
元の由来は分からない儀礼やしきたりで、こんがらがった「繁文縟礼(はんぶんじょくれい)」の武家社会を、格調高い筆でこき下ろす。武家の領地経営の才のなさや、商人たちへの借金を踏み倒す伝家の宝刀「お断り」の仕組みを説明する筆は軽やか。決して厳かではない、自由な神様たちを闊歩(かっぽ)させている。
隠居は、あるときは茶人・一狐斎、あるときは百姓・与作、あるときは板前・長七などに身をやつす才能あふれる怪物。一方の和泉守は、けなげに頑張る若者。周囲を彩る家臣や老中、商人、豪農もそれぞれにキャラ立ちして、存在感を示す。ことに和泉守の兄の舅(しゅうと)となる旗本の御殿様は鮭(さけ)好きで、鮭への愛を語られると、そんなに好きでもないのに食べたくてたまらなくなった。
江戸時代の知見も、人間の洞察も十分だから、虚実取り混ぜその上に織り上げられた物語が生き生きと躍動し、物語に引き込まれずにはいられない。
もちろん笑っているだけではない。和泉守と産みの母は足軽に下げ渡されていた。育ての父との別れや再会、そしてその人となりに目頭を熱くする。怪物だった隠居の本当の姿を読み解いてみせられ、胸に迫るものがあった。そんなふうに、ほろりとする場面が随所に潜む。浅田作品に抜かりはないのである。
ちなみに越後丹生山藩は架空の設定。
プロフィル

ないとう・まりこ 1959年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。87年に毎日新聞社入社、宇都宮支局などを経て92年から学芸部に。2000年から文芸を担当する。同社編集委員を務め、19年8月に退社。現在は文芸ジャーナリストとして活動する。毎日新聞でコラム「エンタメ小説今月の推し!」(奇数月第1土曜日朝刊)を連載中。
内藤麻里子の文芸観察






