栄福の時代を目指して(14) 文・小林正弥(千葉大学大学院教授)
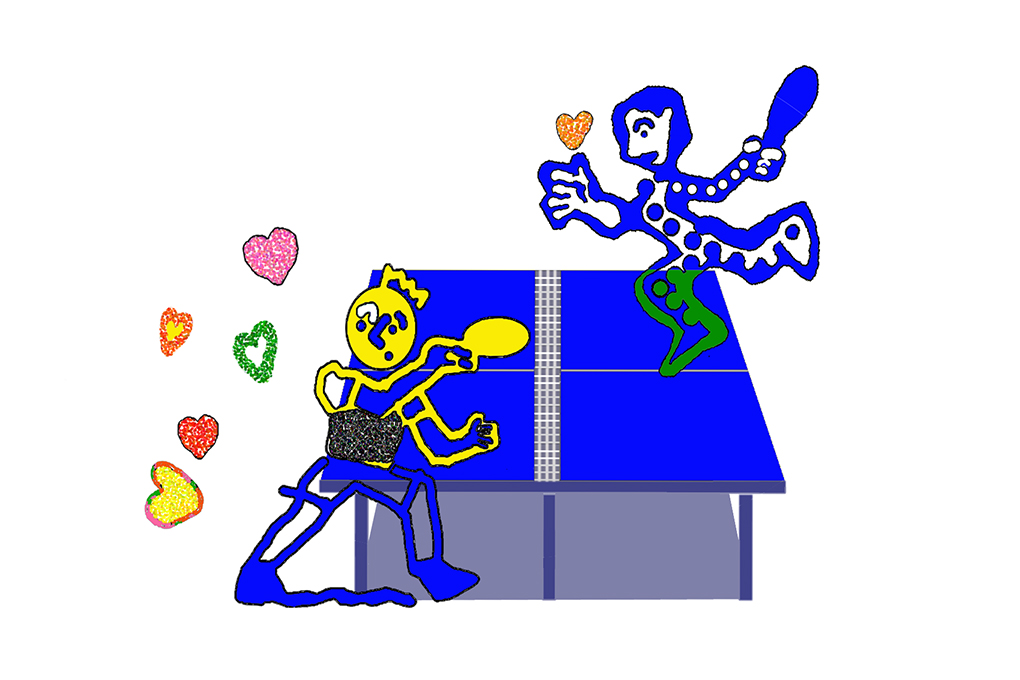
画・国井 節
国難の到来――再び日中戦争や経済破綻に向かうのか?
先月に深刻な懸念を書いてから1カ月も経たないうちに、まさに国難が到来した。そこで今回も政治的論評に集中する。
高市政権が発足してから、悪しき予感がいや増すばかりだった。アメリカのトランプ大統領の訪日時には原子力空母上で、大統領が高市早苗新首相の肩を抱き寄せて称賛し、首相は笑みを浮かべ、ピョンピョンと飛び跳ねて右手を突き上げた(共同通信、10月28日)。その映像にこの世のものとは思えないようなおぞましさを感じ、初めは合成かと疑った。真実のものとわかって呆然とし、「媚(こ)びている」「ホステスみたい」という批判が巻き起こるのを見聞しつつ、軽佻浮薄(けいちょうふはく)な不見識を改めて感じて憂慮した。ポジティブ心理学を研究する身としては、個人的な人生に関しては、前向きな明るい気持ちを保つように努めているものの、日本全体を思う時には鬱々(うつうつ)たる気持ちに襲われる。いかに個々人が努めようとも、戦争や経済的破綻が生じてしまっては、自分自身も、また同胞の人々も幸せではあり得ないからだ。
案の上、首相は、台湾有事で「存立危機事態」になるかもしれないと以前に発言していたので、衆院予算委員会でこれについて問われ、「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだ」(11月7日)という歴史的大失言を行った。国難の始まりだ。
これは、安倍政権が強行した安保法制の核心的問題である。高市首相は、中国が日本に対して何の攻撃を行わなくとも、台湾に対して戦艦を使って武力行使を行えば、日本は同盟国とともに中国に対して武力行使(集団的自衛権の行使)を行えると述べたのだ。普通の言葉でいえば、台湾有事の際には対中戦争を行えると明言したことになる。これは、明らかに日本国憲法第9条の定める平和主義や(個別的自衛権に基づく)専守防衛政策に背反しており、だからこそ、集団的自衛権行使を可能にするこの法律は違憲と激しく批判されたのである。
このような解釈が中国を激しく刺激することは明らかなので、安倍政権も含めて政権は、この論点について曖昧(あいまい)にするという戦略をとってきた。高市首相はそれを破ってしまったのだ。
そのため、中国が強烈な抗議を行い、発言撤回を求めるとともに、日本への渡航自粛勧告や留学自粛勧告を行い、続けて水産物禁輸という経済制裁を発動した(11月19日)。
新しい具体的問題が日中間や台湾に生じたわけではなく、必要もないのに高市首相が中国を激怒させたのだから、トランプ大統領もこの紛争について聞かれても「多くの同盟国だって友人とは言えない。中国以上に貿易で我々を利用してきた」(11月10日)と答えて中国批判を避け、台湾や韓国も距離を置いている。要するに、関係諸国も迷惑だと思って世界で孤立したのだ。中国との紛争はエスカレートしつつあり、日本経済の悪化や、最悪の場合は将来の(一定の時間とプロセスを経てからの)武力衝突への発端となることが懸念される。
共同通信社がこの発言についての賛否を問い、(どちらかと言えば、も含めて)賛成48・8%、反対44・2%という結果(11月16日)を見て、絶句した。集団的自衛権を行使すれば、日中戦争になる。これは、まさしく亡国への道だ。
高市首相は、答弁後に周囲に「つい言い過ぎた」と漏らした、と報じられている(朝日新聞、11月21日)。つまり、政府部内の検討も同意もなしに首相個人が国会で行った独断的発言だから、この責任は全面的に首相本人にある。発言の撤回か辞任しか、早期事態収束の方法が見つからない。経済政策はアベノミクスを踏襲するもので準備中の経済対策も巨額と報じられているから、中国の紛争によるダメージと相まって、株安・円安・国債安(金利上昇)というトリプル安が生じて、急速な物価上昇へとつながることが懸念される。外交と経済の路線を急旋回しない限り、国難を回避する術(すべ)はないだろう。安倍晋三元首相らは「悪夢の民主党政権」と非難を続けたが、この用語法を用いれば「悪夢の高市政権」と言わざるを得ない。
この構図を、巨視的な角度から考えてみよう。
今なおファシズムの時代なのか?
2016年に「今なおファシズムの世紀なのか?――日本における政治循環と新権威主義」(『公共研究』第12巻第1号)という論文を書いた。大学の学部時代の恩師・篠原一先生が亡くなられたので、追悼の気持ちを込めて執筆した比較政治の論考だ。篠原先生は、ヨーロッパ政治の研究者で、「歴史と政治が出会うところ」というフレーズで表されたように、この双方を架橋する歴史政治学を開拓されて、前回も書いたように、ヨーロッパの連合政治を日本に紹介され、市民とともに歩んで市民の政治学も展開された。私は、その薫陶を受けて比較政治学を研究し始めたので、学恩を思い起こしつつ、当時の世界と日本の情勢を憂えて書いたのである。
ネオ・コーポラティズムという概念も紹介されて、当時の私は大いに関心を持った。他方で政治思想を学ぶと、ネオ・リベラリズムという考え方が世界に大きな影響を及ぼしていることがわかった。サッチャー政権やレーガン政権、日本では中曽根政権や小泉政権などがこの思想に影響を受けて、民営化や規制緩和を行い、自己責任論を流行らせた。
その後、自分自身の研究で、日本政治の構造を説明するために、ネオ・クライエンテリズム(新恩顧主義)やネオ・パトリオティズム(新家産制)、新封建制という概念を用いた。また、世界中で民主主義から専制的な体制へという移行が起こり始めており、それを新権威主義(ネオ・オーソリタリアニズム)とも呼んだ。
なぜ比較政治学や政治思想の概念で、「ネオ(新)」という概念がかくもしばしば用いられるのだろうか? このような問題意識を持って今日の政治を見ると、前近代的な政治や戦間期の政治が、若干形は変えつつも再生しており、だからこそ「ネオ」を冠した政治的概念が頻繁に用いられているのではないか、と思い至ったのだ。今、同じような洞察を「フラクタル構造」という概念で説明している(即礼君の物語)。
そこで「いまなおコーポラティズムの政治なのか?」(フィリップ・C・シュミッター)という有名な研究(ネオ・コーポラティズム論)に倣って、論文のタイトルを付した。当時、つまり今から10年前に、私は、安倍政権が改憲を行って戦前のような権威主義的体制へと変えてしまうのではないか(上からの準極右的体制変革)、と心配していたからだ。
極右的なポピュリズムや権威主義的民主主義が世界的に勃興し始めているので、ファシズムに似た政治が近未来に現れてくるのではないかという悲観的な予想をして、この論文ではそれを「ネオ・ファシズム」と呼んだ。つまり、ファシズムが、形を変えつつ、再生してくるのではないか、と論じたのである。戦間期のコーポラティズムや権威主義、ファシズムが、議会制を廃止して現れたのに対し、ネオ・コーポラティズムや新権威主義はしばしば議会制を維持したまま混合した形態で現れているので、「混成的政治」と呼んだ。同じようにファシズムも、かつての完全なファシズム(真正ファシズム)そのままの形態ではなくとも、「混成的ネオ・ファシズム」として、議会制を残しつつも形骸化させて現れてくるかもしれない。日本でも、安倍政治が進展すると「混成型ネオ・ファシズム」となっていくかもしれない――「ネオ・ファシズム」という概念を提起することによって、このような危険に警告を行ったのだ。






