カズキが教えてくれたこと ~共に生きる、友と育つ~ (8) 写真・マンガ・文 平田江津子
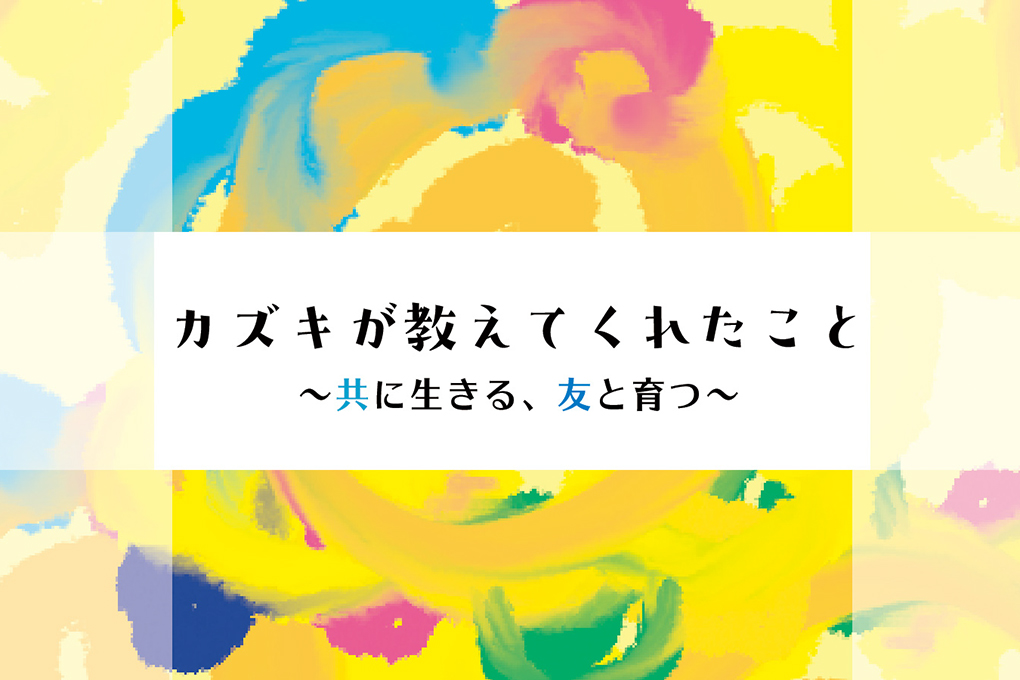
「同じ仲間」として対等に関わる同級生たち①
中学校から普通学級籍となってカズキがいちばん変化したことは、なんといっても友だちとの関係です。小学校時代、特別支援学級籍だったカズキの個性を、当初みんなはよく理解していなかったためか、腫れ物に触るように関わっていたようでした。しかし、中学校では毎日をクラスメイトと一緒に過ごすことで、ここには書ききれないほど、大人の想定をはるかに超えた素敵な関係が育っていったのです。
「カズくん」だった名前の呼び方が、「同じ仲間なんだから、〝カズ〟と呼ぶ!」と言い出した生徒の影響で、みんなが「カズ」と呼び始めました。体育のバスケットボールの授業では、カズキにもボールがしっかり回るような「カズルール」をみんなで考え、共に試合に臨むことができました。生徒それぞれのやり方で手を貸し、一緒になって遊び、「同じ仲間」としての関係性が自然にできていきました。

家庭科の調理実習でハンバーグを作った時のこと。タネをこね終わり、いざフライパンへという場面で、担任の曽我部昌広先生が「ここで落としてしまったら大変! 自分がやろうかな……」と周りの生徒につぶやきました。生徒たちは「大丈夫、できるよ!」とカズキにやらせてみると、問題なく成功したのです。子どもたちは何事にも、「カズキはできる、一緒にやる」が前提です。みんなにとってカズキは、決して「かわいそう」とか「やさしくしてあげる」といった存在ではなく、他の友だちと何ら変わらない 〝対等〟な関係性であるため、何事にも良い意味で容赦がないのです。「大人はこうやって、子どもから大事なものを奪ってしまっているのかも……」と、曽我部先生と共にかみしめた出来事でした。

中学3年生の時のことです。いよいよ修学旅行が近くなり、私がカズキの代理で班のグループラインに誘ってもらいました。するとすぐに、「家に遊びに行ってもいいですか?」という夢のようなメッセージが! その日からたくさんの友だちが、わが家に遊びに来るようになりました。一緒に遊ぶ姿は無理なく自然で、何よりカズキの表情がとても良いのです。家族には見せたことのない、友だちと「折り合い」をつけて一緒に行動するカズキの姿に、想定外の成長を感じたものでした。
「カズキとの旅行、楽しみ過ぎます!」「俺たちに任せてください」という友だちからのラインに、安心と楽しみで迎えた修学旅行。演劇鑑賞では、生徒たちの必死の「しー!」で最後まで席を立たずにいられました。バスの中では、カズキが口ずさんだ歌に手拍子が始まり、みんなで大合唱になったといいます。最終日には、曽我部先生からたくさんの感動場面とクラスメイトたちの成長の喜びにあふれた報告メールが届きました。
「カズキのおかげです。信念を通してカズキをこの学校の普通学級に入れてくださりありがとうございます」
カズキを産んで以来、いちばんのうれし涙を流した日となりました。
プロフィル

ひらた・えつこ 1973年、北海道生まれ。1男3女の母。立正佼成会旭川教会教務部長。障害のある子もない子も同じ場で学ぶインクルーシブ教育の普及を目指す地元の市民団体で、同団体代表である夫と二人三脚で取り組みを進めている。






