「ウィズコロナ時代」へ 識者の提言(2)
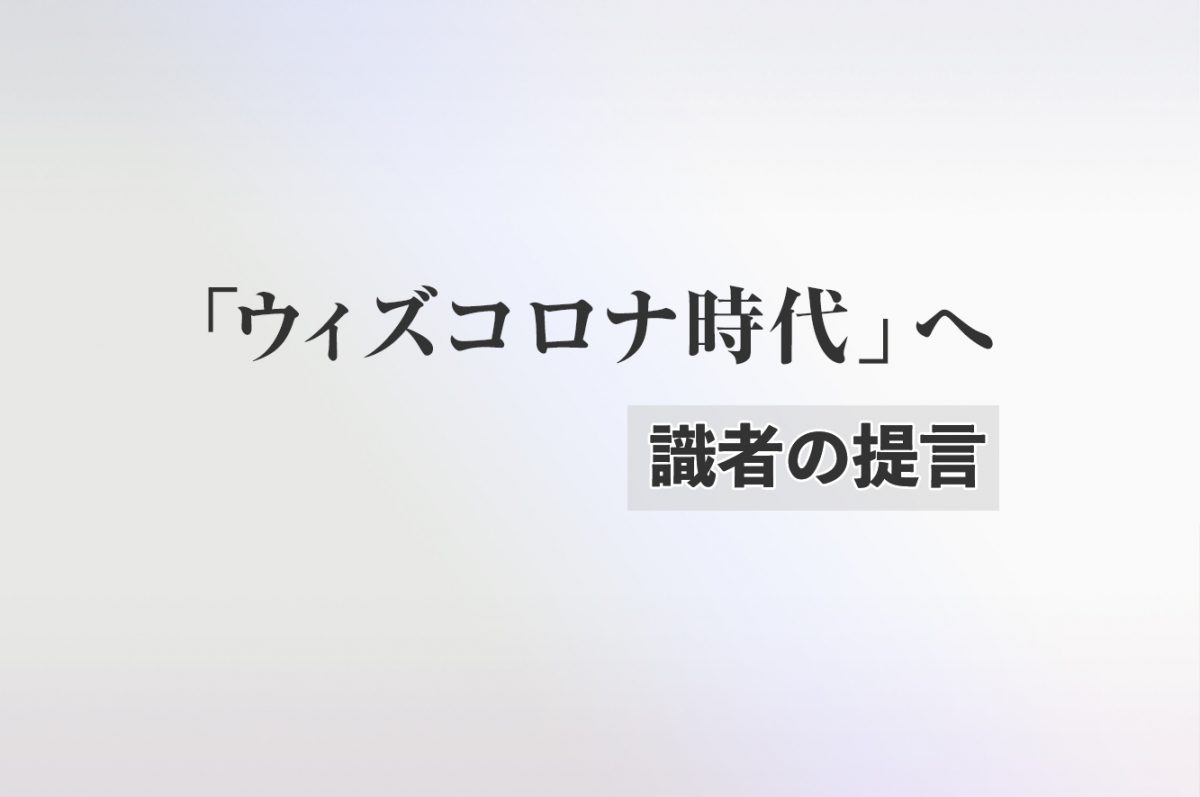
新型コロナウイルスの感染拡大によって、人々の日常生活から世界経済に至るまで「想定外」の大きな変化が起きている。「ウィズコロナ時代」を迎えて、何を大切にし、どのような考えを持っていけばいいのか――2人の識者の提言(寄稿)を紹介する。
ウィズコロナと文学 文芸ジャーナリスト・内藤麻里子
新型コロナウイルスに翻弄(ほんろう)されている今を代表する文学は、なんと言ってもアルベール・カミュの『ペスト』(新潮文庫)であろう。1947年にフランスで発表された同書は、感染が拡大する中で36万4000部が増刷され、累計発行部数は125万部に上るという。
同書は、ペスト感染を抑えるため、封鎖された都市を舞台に、そこで生きる人々の姿を描く。ペストという災禍は今までメタファー(暗喩=あんゆ)として読まれてきた。発表当時のそれは第二次世界大戦であり、最近では東日本大震災の後も注目された。しかし今回は、同じ感染症の問題という点で切実さが格別だった。

そこに書かれた愛する者との別離や希望的楽観論、偏見による差別など不条理に直面した時の心理、行動はすべて心当たりがある。70年以上前に書かれた普遍の人間性の内に、しょせん我々もいるのだと思うと安心するのか、慄然(りつぜん)とするのか。ともあれ、同書は「ウィズペスト」を宣言して終わる。我々は「ウィズコロナ」の日常を受け入れなくてはならない。
昨年中にコロナを扱った作品の刊行はまだ多くない。背景なりともコロナ禍が登場するのはこれからだ。海堂尊さんの『コロナ黙示録』(宝島社)は、2019年11月から20年5月までを戯画的に描いている。ご本人が医学博士であり、手掛けた医療ミステリーの設定を使っていち早く書いた作品である。
『ホスト万葉集』(短歌研究社発行、講談社発売)は、歌舞伎町のホスト75人が詠んだ短歌集だ。ホストと聞いて、イロモノと思わないでほしい。言葉を獲得して、心情や情景を表現しようとした歌は案外と心にしみる。本の製作途中でコロナの感染が拡大し、最終章にその時期の歌を集めた。“夜の街”とやり玉に挙がった街の住人の声として、貴重な証言だ。そこから1首紹介しよう。
〈「伝えたい会えない日々が続くから」振込先の口座番号〉
好きな物語と出会えるサイト「tree」では、20年4月1日以降の日本を舞台に、掌編小説を毎日1本ずつアップする「Day to Day」を企画した。「小説の力で、(中略)心を明るくできますように」と願い、辻村深月さん、東野圭吾さんら100人が小説やエッセイで希望を託し、現状をえぐっている。

小説の力という意味では、直接コロナに関係ないが、明日また頑張ろうと思う力をくれる作品もある。伊坂幸太郎さんの『逆ソクラテス』(集英社)は何らかの常識、常態を覆そうとする子供たちが活躍する短編集だ。彼らの心根をつづる言葉が、コロナ禍で腐っていたところにさわやかな一陣の風を吹きつけてきた。池上永一さんの『海神(わだつみ)の島』(中央公論新社)は、飛び切り面白い冒険活劇だ。沖縄を舞台に、秘宝をめぐる3姉妹のあの手この手の争奪戦が展開する。沖縄が抱える諸問題も核心を突いて描き、充実のエンターテインメント。疲れた心に充足感があふれた。これらは確かに小説の功徳なのである。
文学ではないが、斎藤幸平さんの『人新世(ひとしんせい)の「資本論」』(集英社新書)にも少し触れておきたい。新型コロナウイルスは、自然を開発しすぎたことによって人間に感染したと言われる。我々は経済成長はもう無理だとうすうす感じている。これからは「脱成長」だと斎藤さんは指摘する。脱成長時代はウィズコロナの時代といってもいいだろう。
そんな中、五木寛之さんのエッセイ集『大河の一滴』(幻冬舎)が昨年、単行本、文庫合計34万部増刷されたことに注目したい。1998年発行、累計で320万部超と、そもそもロングセラーだが、この時代を生きる知恵が詰まっている。私たちに往々にして訪れる「これからどうしよう、と、ため息をつく場面」を、「心が萎(な)えた」状態と言う。「『人が生きるということは苦しみの連続なのだ』と覚悟するところから出直す」など、生き抜く方法を人生の深みから丁寧に説いてくれる。
【次ページ:コロナが浮き彫りにしたもの、これまでと今後の文明】






