切り絵歳時記 ~柳田國男『先祖の話』から~ 8月 文/切り絵 ルポライター・切り絵画家 高橋繁行
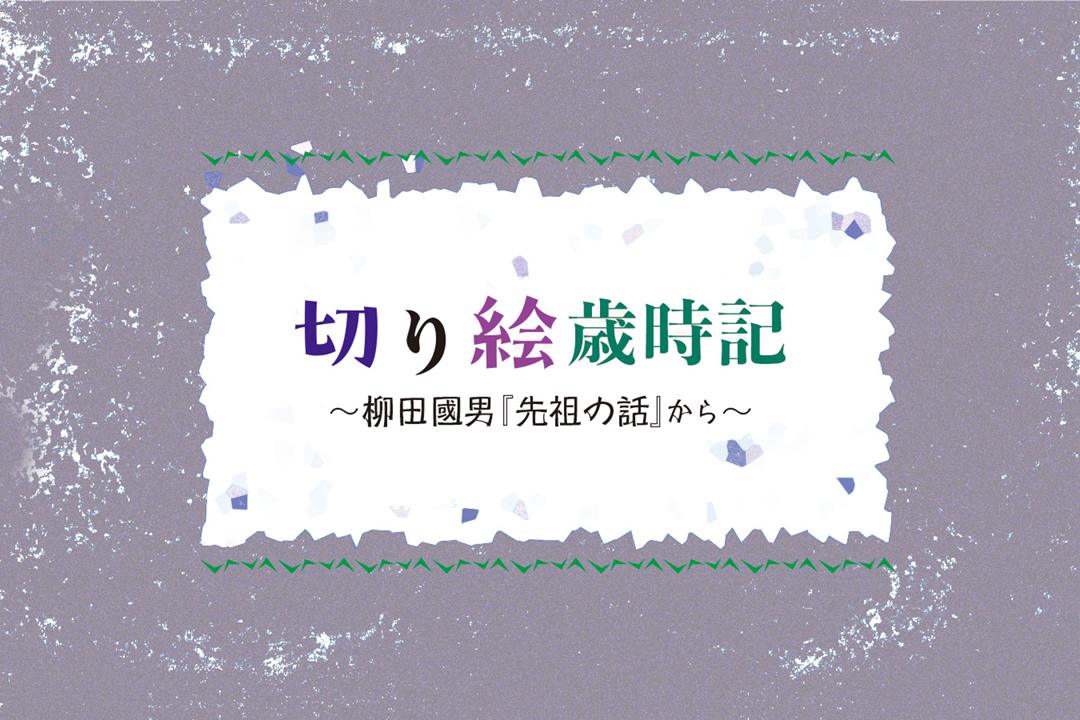
人は死ねば子孫の供養や祀(まつ)りをうけて祖霊へと昇華し、山々から家の繁栄を見守り、盆や正月に交流する――柳田國男は膨大な民俗伝承の研究をもとに日本人の霊魂観や死生観を見いだした。戦時下で書かれた柳田國男の名著『先祖の話』をひもときながら、切り絵を使って日本古来の歳時記を絵解きしたい。
このあかり
お盆が近づいてきた。仏教用語の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」の省略形として「盆」と呼ばれる。この連載で何度かお伝えしたが、元々お盆は魂祭(たままつり)と呼ばれる、先祖を迎えるめでたい祝い日だった。けれどもお盆が、ごく最近に亡くなった先祖を迎えて供養する催しに変わっていくと、人々の間で死を不吉なものとして忌み嫌う感覚が徐々に大きくなっていった。
では、盆の祭りはどんなものだったか。『先祖の話』には、郷愁をそそるこんな記述がある。
「たとえば親子兄弟皆健(すこ)やかに日を送り、近年しばらくは不幸も無かったという家は多いのだが、そういう家々の先祖祭は、実はよっぽど楽しい待ち遠なものだった」
「盆を待つ心構えは何よりも食物の支度、家屋家財の拭き磨き、新しい晴着の用意に次いで、子供の戒められるのは蜻蛉(とんぼ)やばったを捕るなということ、喧嘩(けんか)をするな、泣いたりわめいたりしないこと、それを盆さまがひどく嫌わっしゃると、教えている家は決して少なくない」
夏のとんぼを捕るな、という戒めはほほえましい。お盆に先祖さまがとんぼの姿であの世から戻ってくるからだろう。

【お盆 このあかり】
盆を楽しみにした人びとの暮らしはつつましやかだ。貧しくとも豊穣(ほうじょう)でさえあったといえる。筆者の子ども時代も、お盆はただ待ち遠しかった。
お盆の迎え火は通例、墓の前で焚(た)いてその火を提灯(ちょうちん)に移し、祖霊を迎える所が多いという。火を灯(とも)すのは子どもの役で、先祖を招くこんな素朴な招魂の辞を口々に唱えた。
盆さん盆さん
このあかりでございやあし
「このあかり」は迎え火を焚く時の唱えごとだったそうだ。
「それが夜の空に照り輝くのを、遠くから美しいと眺めていた人々が、これを祖霊の道しるべのごとく、考え始めたのも至って自然である」と、同書は説いている。
プロフィル

たかはし・しげゆき 1954年、京都府生まれ。ルポライター・切り絵画家。『土葬の村』(講談社現代新書)、『お葬式の言葉と風習 柳田國男「葬送習俗語彙」の絵解き事典』(創元社)など、死と弔い関連の著書を手がける。高橋葬祭研究所主宰。






