切り絵歳時記 ~柳田國男『先祖の話』から~ 9月 文/切り絵 ルポライター・切り絵画家 高橋繁行
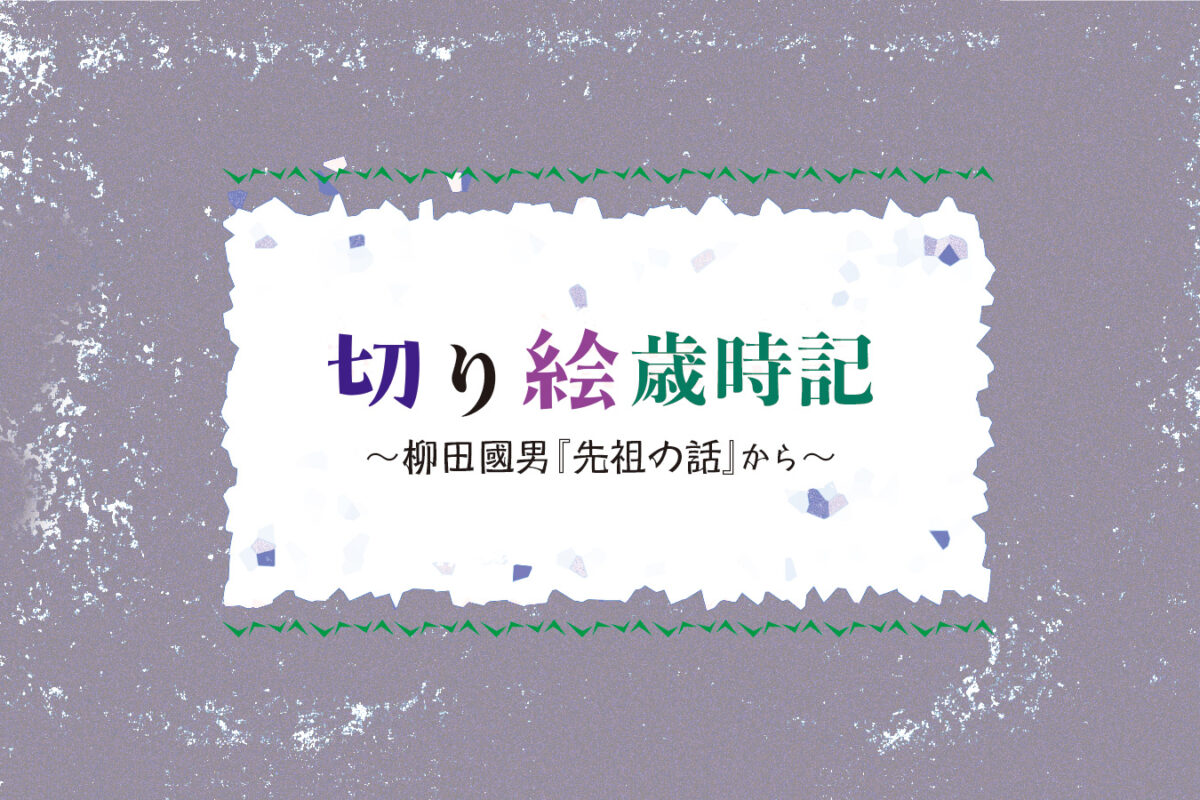
人は死ねば子孫の供養や祀(まつ)りをうけて祖霊へと昇華し、山々から家の繁栄を見守り、盆や正月に交流する――柳田國男は膨大な民俗伝承の研究をもとに日本人の霊魂観や死生観を見いだした。戦時下で書かれた柳田國男の名著『先祖の話』をひもときながら、切り絵を使って日本古来の歳時記を絵解きしたい。
おしらボトケ
『遠野物語』に登場するオシラサマ(「おしら様」とも)は、東北地方一帯で古くから信仰される民俗神だ。さまざまなご利益をもたらす家の神として祀(まつ)られ、桑の木に何枚も着物をまとわせた人形(ひとがた)として広く知られている。同地域では、この桑の木人形もホトケに含まれ、「おしらボトケ」と言われた。
『先祖の話』に信仰行事として「おしら様の祭日」が紹介されており、「三月と九月の十六日が最も多く」とある。この祭日を「おしらボトケ」と呼んだ。
どのような祭日なのか。同書には「もとは春秋の御縁日にホロクまたは遊ばせると称して、女や子供などの縁のある人々が寄り集まり、古く伝わった語りごとを聴き、それに伴う簡単な舞の手振りを見て、神と共に一日を楽しみ暮らす」と記述されている。

【おしらボトケ】
「語りごと」とは、巫女(みこ)のイタコが唱えるおしら様の祭文を示す。集まった人々は、イタコの祭文を聴きながら、おしら様の舞姿を楽しんだ。
ここで著者の柳田國男は、面白い疑問を投げかけている。一般によく、亡くなった人のことをホトケと言う。それなのにどうして、喪(も)と何の関係もないものをおしらボトケと呼んだのか。そもそも亡くなった人をホトケと呼ぶようになったのはなぜか。
正解の一つを、ホトケの語源とされる「浮屠(ふと)の木」に見いだすことができる。浮屠とは仏陀(ぶっだ)。つまり、亡くなった人を「お釈迦さまの木像」に見立てて拝み敬ったというわけだ。ホトケと呼ぶようになったゆえんである。
それならどうして、「おしら様」のような、葬式と直接関係がない桑の木の人形までホトケと呼んだのか。理由は、おしらボトケでは、木の依座(よりまし)を使って拝むに値する、自分たちの神を信じる習わしが昔から東北地方にあったからだとしている。言い換えると、遠野に伝わる仏教以前の古代民俗信仰の神を敬い、それを「(おしら)ホトケ」と呼んだのである。
プロフィル

たかはし・しげゆき 1954年、京都府生まれ。ルポライター・切り絵画家。『土葬の村』(講談社現代新書)、『お葬式の言葉と風習 柳田國男「葬送習俗語彙」の絵解き事典』(創元社)など、死と弔い関連の著書を手がける。高橋葬祭研究所主宰。






