切り絵歳時記 ~柳田國男『先祖の話』から~ 6月 文/切り絵 ルポライター・切り絵画家 高橋繁行
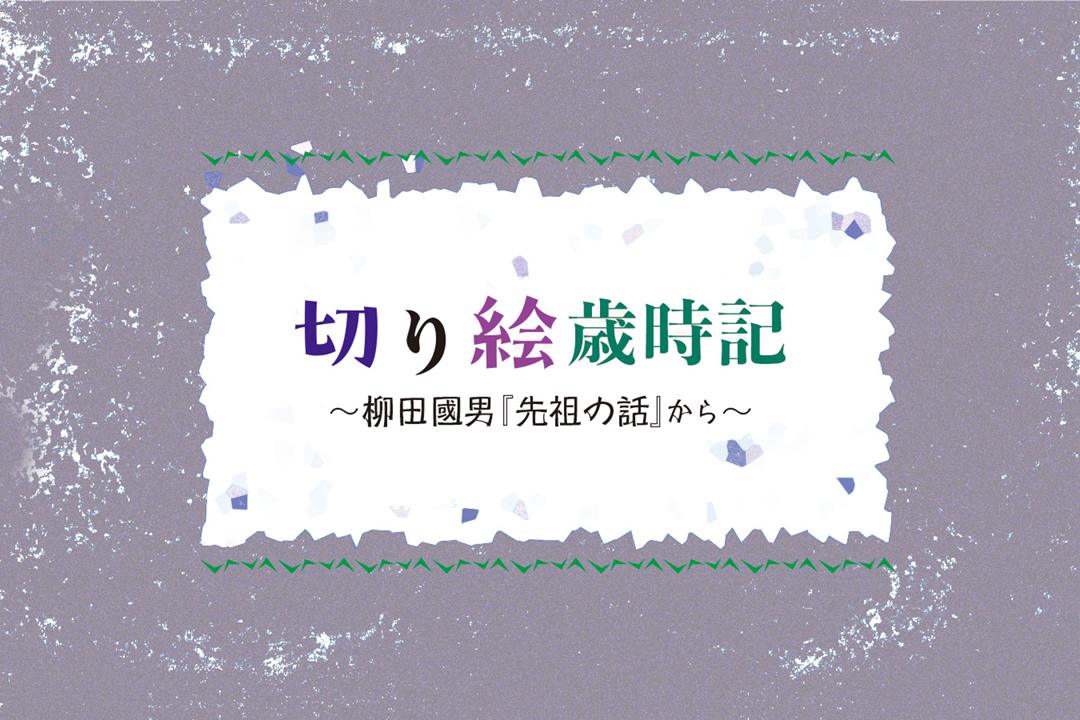
人は死ねば子孫の供養や祀(まつ)りをうけて祖霊へと昇華し、山々から家の繁栄を見守り、盆や正月に交流する――柳田國男は膨大な民俗伝承の研究をもとに日本人の霊魂観や死生観を見いだした。戦時下で書かれた柳田國男の名著『先祖の話』をひもときながら、切り絵を使って日本古来の歳時記を絵解きしたい。
六月朔日は赤ちゃんの歯固め
平安時代から、六月朔日(ついたち)は「歯固めの日」と呼ばれる。歯固めとは、生まれて間もない赤ちゃんに餅を食べさせ、長寿と健康を祈るたいへん古い習わしだ。
歯固めに関連づけて『先祖の話』では、「魂祭(たままつり)」と呼ぶ、先祖祭の風習を取り上げている。この先祖祭の日に「みたまの飯(めし)」という握り飯の形状によく似たものを供えたという。面白いのは、みたまの飯を保存しておいて、「六月朔日の歯固めに炒(い)って食べ」と書かれているところだ。生えてきたばかりの赤ちゃんの歯が丈夫に育つように、固い握り飯を食べさせたというわけである。
は歯固めの日_R-500x621.jpg)
【六月朔日は歯固めの日】
さて、このみたまの飯だが、切り絵をご覧いただきたい。十二個の丸いおむすびを作り、てっぺんに一本箸を立ててある。つまり、死んだ人の枕辺に供える枕飯とまったく同様のことをするのだ。
先祖祭という祝い事の供え物と、葬儀の食べ物が、どうして同じなのだろう? 元来、魂祭は、ご先祖を「みたま」と称して祀(まつ)る喜ばしい祝い事であった。年の暮れや正月だけでなく、五月五日の端午、九月九日の重陽まで五節供(せっく)にみたまの飯を、他の節日の料理と一緒に食べてこの日を祝った。ご先祖の霊はみたまと恭しい名で呼ばれたのである。お盆はどうだろう? 実は、お盆もまたこれらと同様、先祖を祀る祝い事の祭り日だった。
ところが、お盆は、ごく最近に亡くなった先祖をお迎えして供養する催しへと変化していった。ご先祖をみたまと呼ばず、「新精霊(にいじょうろ)」と呼ぶようになった。死を不吉なものとして恐れ、喪(も)の穢(けが)れを忌み嫌う感覚が徐々に大きくなってきたといえる。
本来不吉なものではなかった枕飯も、今では「縁起でもないことだ」と戒められるようになったゆえんである。
『先祖の話』では、「もとは正月も盆と同じように、家へ先祖の霊の戻って来る嬉(うれ)しい再会の日であった」と結論づけている。
プロフィル

たかはし・しげゆき 1954年、京都府生まれ。ルポライター・切り絵画家。『土葬の村』(講談社現代新書)、『お葬式の言葉と風習 柳田國男「葬送習俗語彙」の絵解き事典』(創元社)など、死と弔い関連の著書を手がける。高橋葬祭研究所主宰。






