人類救済の“二千年祭”に向けて世界に散在する枢機卿が選ぶ新教皇(海外通信・バチカン支局)
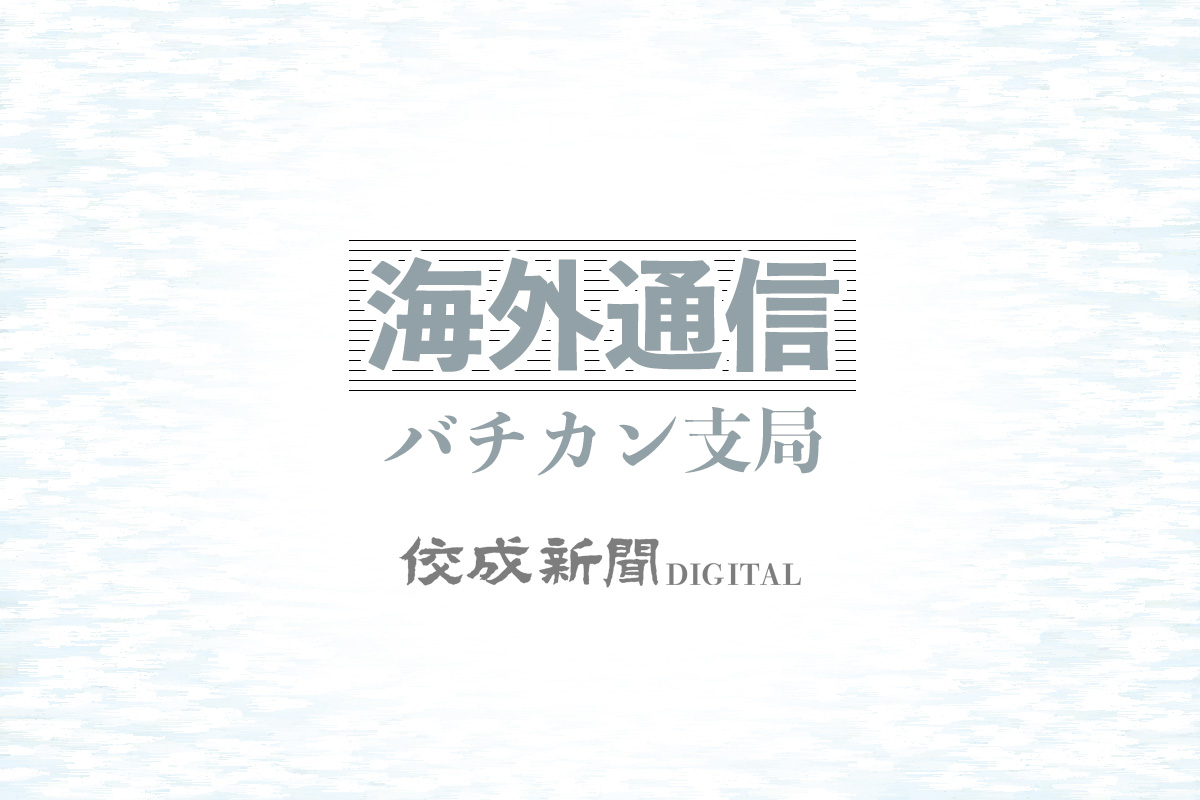
ローマ教皇ベネディクト十六世が選出された2005年の教皇選挙(コンクラーベ)では、事前の下馬評で、長年にわたりバチカン教理省の長官を務めていた、ドイツ人のヨゼフ・ラッツィンガー枢機卿が唯一の候補者として挙げられた。予想は的中し、同枢機卿は2日間にわたる4回の投票で新教皇に選出された。
教皇ベネディクト十六世の生前退位を受けて13年に執り行われた選挙では、アルゼンチン人のホルヘ・マリオ・ベルゴリオ枢機卿が2日目の第5回投票で選出され、フランシスコを名乗った。教皇フランシスコは、昨年刊行した自叙伝の中で、教皇ベネディクト十六世が選出された05年のコンクラーベで初投票時に自身が40票を得たが、それは「私を教皇にするためではなく、票割れによってラッツィンガー枢機卿の選出を阻止し、第3の候補者を擁立するためだった」と明かした。だが、13年のコンクラーベでも、「ベルゴリオ枢機卿を擁立すれば40票は確保できる」との確信は残ったようだ。さらに、ベルゴリオ枢機卿は、ある枢機卿から「あなたは、肺に疾患があるそうだね」と尋ねられた時、「自身が教皇候補に挙げられていることを感知した」とも記している。

前世紀には10回のコンクラーベが執り行われたが、1903年の教皇ピオ十世の選出には4日間、14年のベネディクト十五世は3日間、22年のピオ十一世は最も長い5日間、39年のピオ十二世は2日間、58年のヨハネ二十三世は4日間、63年のパウロ六世は3日間、78年のヨハネ・パウロ一世は2日間、同じく78年のヨハネ・パウロ二世は3日間にわたる投票後に選出された。
コンクラーベでの投票は、選出に必要な3分の2の得票率を求めて、初日午後に1回、2日目からは午前・午後に2回ずつ行われる。3日後に得票率が規定に達しなかった場合、一日の祈りと枢機卿間での対話の時間が設けられる。その後の投票でも選出されなかった時は、一日の祈りと対話の期間を置いて、7回を一単位とする投票が最高4回繰り返される。それでも未決の場合、前回投票で最多得票数を得た2人の決選投票に移行されるが、選出に必要な得票率は3分の2のままだ。
1268年から71年まで、ローマ近郊のヴィテルボで開かれた最初のコンクラーベは1006日間も続いた。絶望したヴィテルボ市民が、枢機卿たちを選挙会場に鍵をかけて閉じ込め(ラテン語でclausi cum clave/コンクラーベの語源)、食事も水とパンだけとし、最終的には選挙場の屋根瓦を外して抗議した。結局は、教皇グレゴリオ十世が選出されてヴィテルボでの長い選挙は終わった。
今回のコンクラーベでは、投票権を持つ80歳未満の枢機卿135人のうち、80%が教皇フランシスコによって任命されている。大陸別分布は、アフリカ大陸17カ国(18人)、アメリカ大陸15カ国(37人/北米16人、中米4人、南米17人)、アジア17カ国(23人)、欧州18カ国(53人)、大洋州4カ国(4人)となっている。教皇フランシスコが施行した“世界の僻地(へきち)”からの枢機卿任命政策によって、教皇選挙の有権者が世界中に散在しており、相互に知り合っていないのだ。過去の、欧米を中心としたカトリック教会の勢力図が完全に変わり、教皇選挙と、その候補者に関する予測が非常に難しくなっている。

新教皇の決定を知らせる白煙が上る煙突の取り付け作業(バチカンメディア提供)
4月22日に開始されたコンクラーベに向けての「枢機卿会議」も、「今回の教皇選挙は難航するのではないか」と言われて始まった。『世界とカトリック教会』をテーマに討議しながら、提供された全有権者である枢機卿の写真入り略歴に目を通し、新教皇のイメージを模索していった。
教皇フランシスコの葬儀から9日間は喪に服す期間と定められ、毎日、聖ペトロ大聖堂(サンピエトロ大聖堂)で代表枢機卿の司式する追悼ミサが捧げられている。2日目(4月27日)のミサを司式した国務長官のピエトロ・パロリン枢機卿は、ミサ中の説教で、主なるキリストを十字架上で失った使徒たちの孤独、喪失、恐怖、虚無感に言及しながらも、「“慈しみ”が神の名である」と説いた教皇フランシスコの教えを、「その時の感情として受け入れるのではなく、実生活の中で実践しなければならない」と呼びかけ、「われわれと神の関係や教会の在り方を、人間や世俗の範疇(はんちゅう)で解釈してはならない」と戒めた。これから始まる教皇選挙に向けた「枢機卿会議」に対する警告とも受け取れる発言だった。






