切り絵歳時記 ~柳田國男『先祖の話』から~ 5月 文/切り絵 ルポライター・切り絵画家 高橋繁行
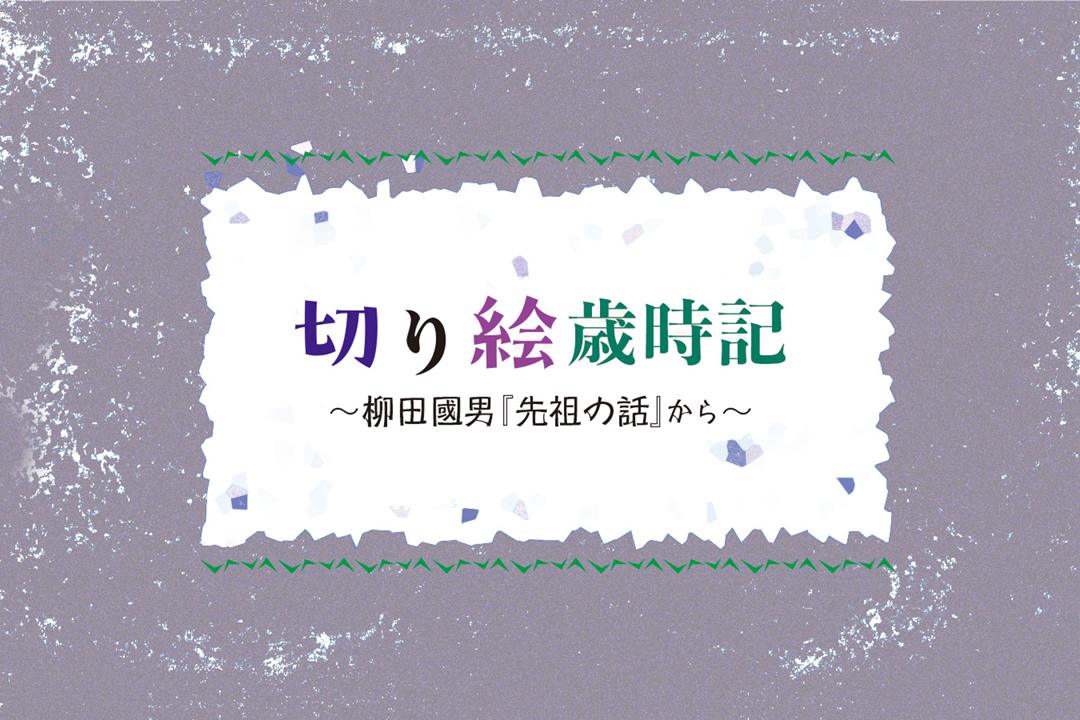
人は死ねば子孫の供養や祀(まつ)りをうけて祖霊へと昇華し、山々から家の繁栄を見守り、盆や正月に交流する――柳田國男は膨大な民俗伝承の研究をもとに日本人の霊魂観や死生観を見いだした。戦時下で書かれた柳田國男の名著『先祖の話』をひもときながら、切り絵を使って日本古来の歳時記を絵解きしたい。
端午の節供は女性天下の日
五月五日は、端午の節供(せっく)。こどもの日。『先祖の話』では、この日を一年で最も大切な祭りの日として「三(さん)とき五節供」という言い方をしている。端午の節供が「五節供」の一つというのはわかる。では三ときとは何か? 三ときは「三 斎(とき)」と書き、正月、五月、九月の十六日のことだという。
つまり、十五夜満月の翌日に行う大切な祭り日を指す。どうして大切な祭り日なのかというと、「ちょうど田植の盛りになる旧五月の十六日を重んじ、この日一日は田にも出ず馬も使わず、家に籠(こ)もって神に仕え、特に白米を飯に炊(かし)いで、神人の相饗(あいあえ/ともに食事をすること=脚注筆者)をするのが普通であった」と解説している。

【滝登りする大鯉と足柄山の金太郎を組み合わせた図柄 】
五月五日は一般に男の子の節供と言われる。ところが、昔から民俗学的に伝わる風習では、五月五日が「女天下の日」とか「女が威張れる日」と言われていたのをご存じだろうか。普通は男の節供とされ、鎧兜(よろいかぶと)、武者人形を飾り、男児の出世を祝うなどと言って鯉(こい)のぼりを立てる。それと真逆の女性優位の風習があったというのはどうしてだろう。
その理由は、早乙女と呼ばれた田植えに奉仕する女性が五月五日の前夜、家に籠もって物忌みの生活を送ったからである。早乙女たちは4月号で登場した田の神に奉仕する重い役目を持っていた。その精進潔斎(しょうじんけっさい)のために籠もった。
早乙女の籠もる“女の家”は、屋根や軒を菖蒲(しょうぶ)とヨモギで葺(ふ)いて魔払いをしたと言われている。鎧兜や、足柄山の金太郎の勇ましい図柄は、その時に考案された魔除けと考えられている。
つまり、五月の節供は、もともとは女性中心のものだったが、男の節供にとって代わり、女性のほうは三月三日の雛(ひな)祭りに入れ替わったのだと受け取られている。
プロフィル

たかはし・しげゆき 1954年、京都府生まれ。ルポライター・切り絵画家。『土葬の村』(講談社現代新書)、『お葬式の言葉と風習 柳田國男「葬送習俗語彙」の絵解き事典』(創元社)など、死と弔い関連の著書を手がける。高橋葬祭研究所主宰。






