「核兵器の使用判断をAIに任せるな/バチカン」など海外の宗教ニュース(海外通信・バチカン支局)
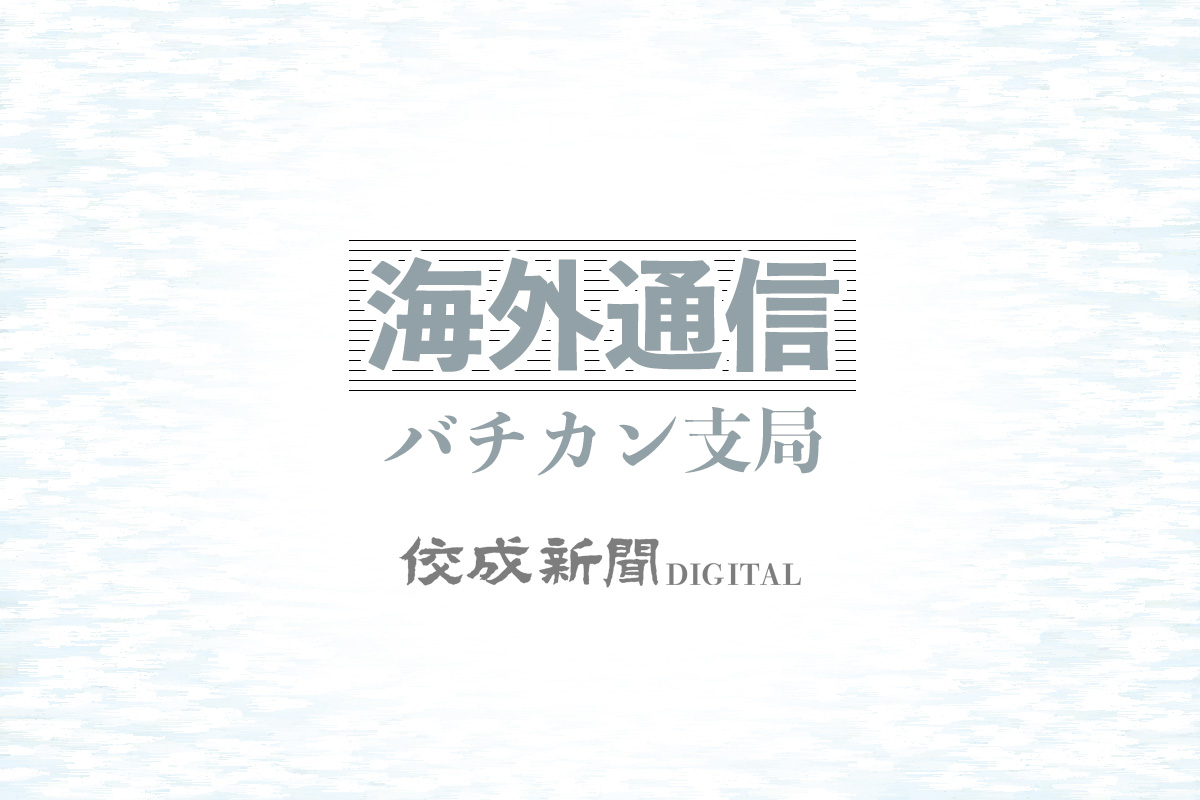
核兵器の使用判断をAIに任せるな/バチカン
米国のトランプ大統領は10月末、訪問中の韓国で、中国の習近平主席との首脳会談を前に、「他の国々が(核)実験のプログラムを持続しているので、それらの国々と平等な立場に立ち、(核兵器の)実験を行うように戦争省(国防総省)に指示した」と明らかにした。「この実験プロセスは、即刻に開始される」との条件付きの公表だった。
この発表は、ロシアのプーチン大統領が「核弾頭を搭載できる原子力推進式の潜水兵器(ポセイドン)や同巡行ミサイル(ブレヴェスニク)の発射試験に成功した」と公表した直後になされたものであり、核爆発を伴う実験ではなく、核弾頭を搭載する新兵器開発のための実験であるとの見方もある。プーチン大統領は現在まで、ロシアによる核爆発を伴う核実験には言及していないが、米国が核実験を再開すれば「それ相応の対処をする」と応酬している。また、米国大統領による核実験再開の公表が、習主席との会談を前になされたことを考慮し、核兵器の大量開発を急ぐ中国に対する牽制(けんせい)としても受け取られている。
米国は1992年来、核爆発を伴う核実験を停止しているが、96年に制定された「包括的核実験禁止条約」(CTBT)に大統領府が署名しているものの、同国上院は未だ批准(ひじゅん)していないという法的空洞があることも指摘されている。こうした米国内での特殊な状況を考慮すれば、トランプ大統領の主張する「即刻なる核実験再開」のためには、「少なくとも36カ月が必要」だとイタリアのシンクタンク「国際問題研究所」のエマヌエル・パネロ氏は指摘する。
トランプ大統領は後に、「核爆発を伴う実験ではなく、核兵器の(使用を有効にする)他の部分に関する実験」と、自身の発言を修正した。にもかかわらず、大統領専用機内で自身が指示した「核兵器実験」について記者団に問われたトランプ氏は9月14日、「言いたくない。他国と同様に実験する」と明言を避けた(15日付「47NEWS」)。機内での新聞記者とのやりとりについて報道するイタリアの「ANSA通信」は15日、トランプ大統領が「米国、中国、ロシアの非核化を望んでいる」と報じた。だが、米国大統領の核実験にまつわる発言は、同国が1952年11月1日、マーシャル群島で実行した水爆実験(広島に投下された原爆の千倍の破壊力)の記念日を数日後に控えてのものだった。さらに、トランプ大統領の「核実験に関する投稿」が憂慮されるのは、ウクライナへ侵攻したロシアによる「第3次世界大戦勃発の可能性や核兵器の使用」をちらつかせた欧米に対する恐喝、2023年にCTBTの批准を撤回したロシア、来年2月に期限切れを迎える米ロ間に残った唯一の核軍縮条約である「新戦略兵器削減条約」(新START)の未来に対する危惧、核戦力を強化しつつある中国、といった国際状況下でなされたところにある。
中ロともに1990年代から核爆発を伴う実験を停止している。こうした中で、米国の役割は、核兵器が人類と地球を完全に破壊する能力を有していることを確信し、核実験や核兵器の開発を助長するのではなく、その縮小と廃絶へ向けた「国際的な枠組み」を主導していくことではないのか。「朝日新聞」は社説(11月1日付)の中で、トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦するとの高市 早苗首相の考えを疑問視し、「戦争被爆国として日本政府の見識が問われる」と強調。日本政府には世界の中で「核軍縮・廃絶への議論を主導する責務がある」と主張した。「国際問題研究所」のパネロ氏は、「核兵器の管理と各国が有する核兵器の削減に向けた目標を達成していくための、国際的な枠組みに関する状況が悪化している」と指摘。トランプ大統領自身も、「米国にとっての最大の脅威は、中国による核戦力の強化」であり、中国をも含む「核兵器の管理に関する国際的枠組み」の必要性を主張していた。
ニューヨークの国連本部で9月3日、核実験の禁止を訴える国連総会が開かれた。その会合でスピーチしたバチカン国連常駐代表(ニューヨーク)のガブリエル・カッチャ大司教は、80年前の最初の原爆の爆発が「歴史の流れを変え、人類の上に長い暗雲を投げかけ」「人間生命と創造(自然)に対して重大なる結果をもたらした」と主張。その結果として生まれた「核抑止論」を「道徳的考察と国際良心に対する挑戦」として受け取り、1945年7月16日に米国ニューメキシコ州で行われた最初の核実験から「2000回を上回る核実験」が行われ、「全ての人々、特に、原住民、女性、子ども、胎児たちに打撃を与えてきた」と糾弾した。さらに、「多くの人々の健康と尊厳が、沈黙の内に、何の賠償をも受けられないまま、害され続けている」と言う。こうした悲劇の前で、「もう二度と繰り返すまい」と誓った人類だったが、世界は「反対方向へと走り」、「攻撃的な核兵器の名を使った説話が、激しさを増してきている」との実感だ。「核兵器から解放された世界の追求」は「戦略的、致命的であるだけではなく、深い道徳的責任に関する問題である」と主張し、「多角的な対話による種々の軍縮条約の早急なる実行」を促すとともに「国際監視と実証システムによって支えられる核兵器禁止条約の重要性」を訴えている。
カッチャ大司教は10月21日、国連総会第1委員会(核軍縮)でも演説した。「核兵器とその増産」が「平和と国際安全保障の最大の脅威である」と警告し、核抑止論について「道徳的に擁護できず、戦略的にも持続できない」と批判。さらに「核兵器の使用、管理、配備などに、人工知能(AI)を導入することは、前例の無い不安を助長する」と警告した。AIの導入が、「判断の時間を短縮し、人間による統制を減少させ、計算間違いの可能性を増長するのみならず、不安をかつてなかったほどのレベルにまで引き上げていく」からだ。
教皇レオ14世は11月20日、イタリアの聖都アッシジで開かれていた同国カトリック司教会議の閉会式に参加し、「キリストへの信仰が、私たちの平和であり、その平和を全ての人に提供するように促されている」とスピーチした。国内外の状況が分断によって支配される中、敵対心や暴力を煽(あお)るメッセージや言語が蔓延(まんえん)し、効率を重要視する傾向が、より弱き者を置き去りにするのみならず、技術万能主義が自由を抑圧していると指摘。「孤独が希望を消費させ、多くの不安定要素がわれわれの将来の重荷となっている」と警告した。これを受けて、イタリアのカトリック司教たちは最終声明文の中で、「平和の王子(キリスト)の名において、諸国民の統治者たちに向かい、武器、特に核兵器を禁止し、平和へのあらゆる努力を為すのみならず、彼らの有する全ての手段を投入して、世界の飢餓と闘うように要請する」とアピールした。また、「人類に対する服喪と悲劇に終止符が打たれ、計測できないほどの恐るべき仮説(核戦争)が回避できるように」と願った。
【次ページ:バチカン宣言文「ノストラ・エターテ」公表に対する庭野開祖の貢献】






