広島、長崎への原爆投下から80年——米国人教皇、大司教たちのメッセージ(海外通信・バチカン支局)
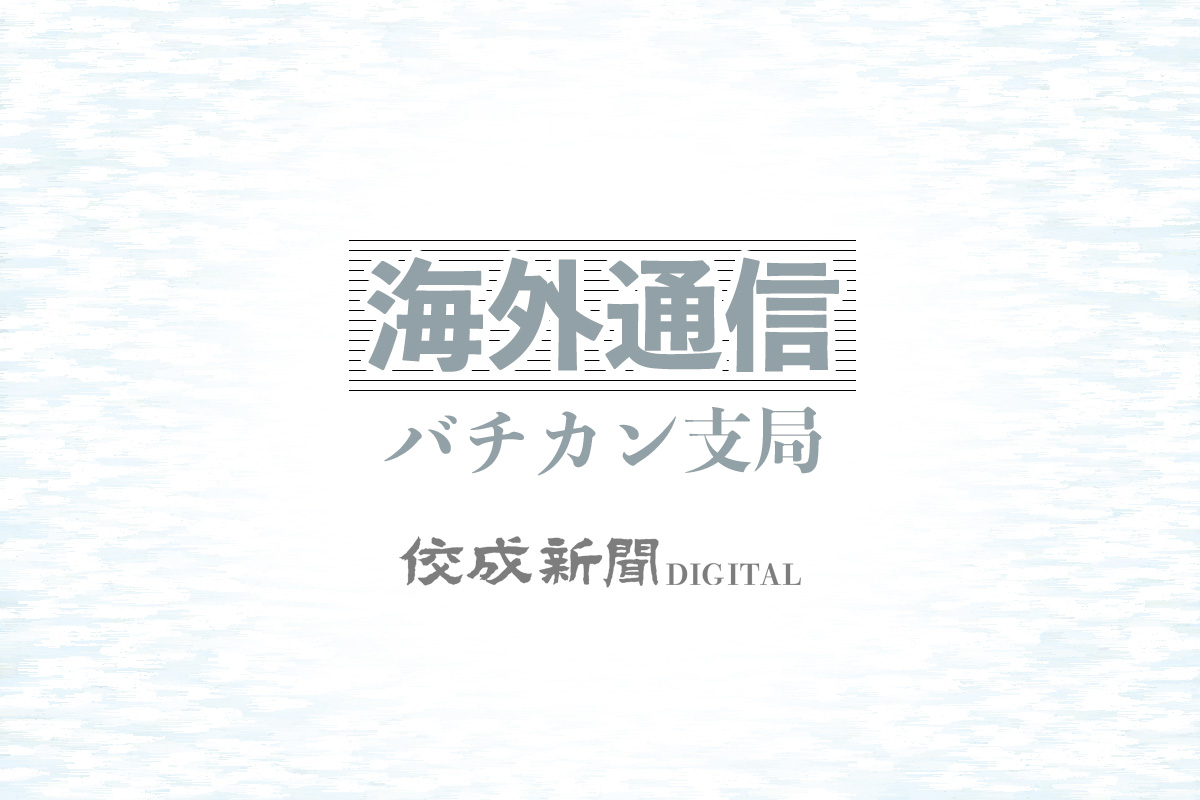
広島と長崎への原爆投下から80年に際して、史上初の米国人のローマ教皇であるレオ14世は、「勇気ある武器の放棄」を訴え、「核抑止論という幻覚」を非難するメッセージを公表していた。8月6日にバチカン広場で執り行われた一般謁見(えっけん)の機会にも、世界から参集した信徒たちに向かい、「今日は広島への原爆投下から80年にあたり、3日後には長崎への原爆投下が思い起こされます」と呼びかけた。「原爆による身体的、心理的、社会的被害を受けた全ての人たち(被爆者)のための祈り」を約束するレオ14世は、「残念ながら、多くの歳月が流れても、あの悲劇的な出来事が、戦争、それも、核兵器によって誘発される破壊に対する普遍的な戒めとして残っている」との反省を促した。「強い緊張と流血の紛争が続く現代世界」にあって、「相互破壊の脅威を基盤とする安全保障という幻覚が、正義、対話の実践、友愛のうちにおける信頼に置き換えられていくように願望」すると語った。
さらに、教皇は10日、バチカン広場で執り行われた日曜日恒例の正午の祈りの機会にも、「世界で戦争に終止符が打たれるように」と願い、「広島と長崎への原爆投下から80年の機会が、戦争を解決の手段として使うことを拒否する義務を、全世界に思い起こさせている」と指摘した。広島と長崎への原爆投下が、「戦争を終わらせたということで本質的には同じだ」として、イランの核施設に対する空爆を正当化したトランプ米国大統領の発言とは真っ向から対立するものだった。世界の政権担当者たちに、「自身の選択がもたらす一般市民への影響を常に考慮するように」と促す教皇は、「最も弱い立場に置かれた人々の必要と、平和に対する普遍の願望を無視してはならない」と警告した。歴代教皇の中で、広島と長崎の「原爆の日」に触れて、3度も続けて核兵器廃絶のメッセージを発したのは、米国人のレオ14世が初めてだった。
米国カトリック教会の広島、長崎での原爆投下80年に関する行事への参加も、注目すべきものだった。過去には、世界で初めて核実験の行われた地区を管轄し、教区内に核実験の被ばく者がいたサンタフェ大司教区のジョン・ウェスター大司教や、シアトル市内の平和公園に被爆者の佐々木禎子さんの銅像を設置している同市のポール・エティエン大司教が、日本へ平和巡礼したことがあった。今年の80年行事には、レオ14世教皇の生誕地であるシカゴのブレーズ・スーピッチ大司教(枢機卿)、首都ワシントンDCのロバート・マケルロイ大司教(枢機卿)が、前述の2人の大司教と共に参加した。
8月7日に長崎で開催された諸宗教者による平和行事でスピーチしたスーピッチ大司教は、原爆製造に向けたプロセスで「マンハッタン計画」が進行中の1944年に、米国人のイエズス会士ジョン・フォード神父が「壊滅を目的とする爆弾の製造を倫理的に容認できない」と糾弾していた事実を指摘し、「核の抑止力という考え方には、現代世界が解決し得なかった倫理的問題として、フォード神父の警告が残る」(8月7日付「バチカンニュース」)とアピールした。米国民の大多数が、広島と長崎への原爆投下に反対する方向へ変化しつつあるが、それと同時に、米国兵士の命を救うための原爆使用を支持する世論も強いと説明し、「米国世論の中で、核兵器を使用して外国市民を意図的に殺害する政策を支持する動きは、予測に反し、1945年以来、そう変わってはいない」と語った。したがって、米国は「反核を基盤とする国際秩序の構築」に努力し、「軍縮の促進と、新閉鎖主義(米国の孤立主義)を拒否」していく責任を有する、と強調した。最後に、スーピッチ大司教は、被爆者に敬意を表し、「核競争に勝者はなく、数百万人の死者が残されるのみ」と述べた。
「世界教会協議会」(WCC)のプレスリリースは5日、世界の80を超える諸宗教共同体が、広島、長崎の被爆80年に際して、「私たちの霊的伝統が、将来へ向けての展望を告げている。人類は、重大な、それも、終末的な害を与える能力を持っているが、生命と福祉のために連帯のうちに協力する能力をも有する」「われわれの持つ倫理と霊性が、核兵器廃絶に向けて協調していくことを促す」と表明し、共同声明文に署名した、と伝えた。
一方で、米国首都ワシントンDCのアメリカン大学のピーター・カズニック教授(核問題研究所所長)は、「現代世界が、1962年のキューバ危機にも増して、核戦争の可能性へと近づいている」「核戦略に関する無秩序(アナーキー)状況の危険性がある」(8月12日付「バチカンニュース」)と警鐘を鳴らしている。
(宮平宏・本紙バチカン支局長)






