食から見た現代(15) “安心・安全”な食の時間〈後編〉 文・石井光太(作家)
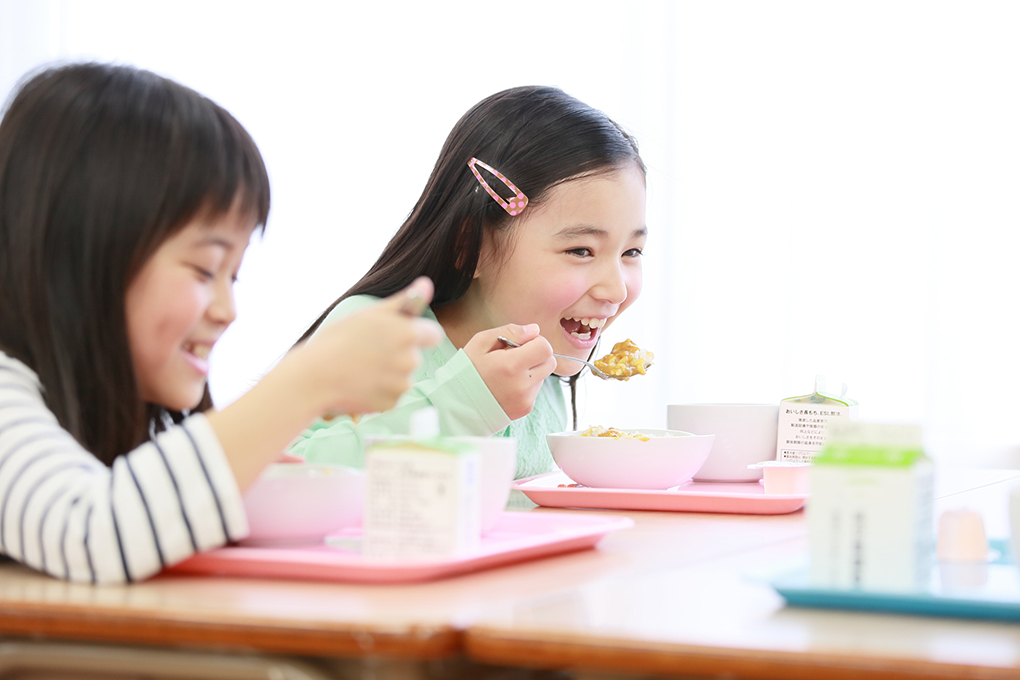
写真はイメージです/© PIXTA
神奈川県相模原市にある児童養護施設「中心子どもの家」には、幼稚園児からおおむね18歳くらいまでの子が、45人暮らしている。
ここのベテラン調理スタッフの1人が、梶道子氏(仮名・67歳)だ。梶氏は、中心子どもの家が海老名市から相模原市に移転した1998年に入職し、四半世紀にわたって勤務しつづけてきた。ただ、児童養護施設が何たるかさえわからないところからのスタートだったという。
梶氏は話す。
「お恥ずかしい話ですが、ここで私が働きはじめた時は、児童養護施設がどういう場所なのか、子どもたちがなぜ連れてこられているのかがわかっていなかったので、スケジュール通りに栄養のあるご飯を出すことだけが調理スタッフの役割としか考えていませんでした。
でも、子どもたちと接している中で、彼らが虐待などでまともに食事を摂ることすら経験できずに保護されてきている状況を知り、ただお腹を満たせばいいわけではなく、食そのものをワクワク感のある楽しいものにすることが重要だと考え直すようになりました。子どもたちが献立を見て心を躍らせたり、食事を前にして会話が進んだりするような工夫をすることで、胃袋だけでなく、心を満たさなければならないと思ったのです」
今も昔も子どもたちに好評な定番メニューは、カレー、ミートソーススパゲティー、ハンバーグなどだ。これらを山盛りにして出せば、子どもたちはたくさん食べてカロリーを満たすことはできるが、食の果たす役割はそれ一つではない。食を通して人と楽しく会話をする、伝統文化を学ぶ、新たな世界に関心を持つといったことも重要なのだ。
それを実現するためには、調理スタッフが意識して調理以外のことも積極的に取り組まなければならない。たとえば、正月のお節料理を通して日本文化を知る機会を提供したり、珍しい外国の料理を出して海外に目を向けさせたりするのである。
2024年の12月であれば、献立の中にあえてインド料理の「サモサ」を入れた。子どもたちの中には、サモサの名前を聞いたこともない人もいるので、献立表に次のようなメッセージをイラスト付きの手書きで書き込んだ。
〈サモサってな~に? サモサはインド料理で手軽に楽しめる軽食といわれています。小麦粉で作った皮でじゃがいもなどをスパイスを利かせた具材を包んだものを揚げたものです。今回はカレー風味にしてみました。食べてみてくださいね!〉
献立表にこう記せば、子どもたちは「サモサって何だろう、美味しいのかな」とワクワクするし、食事中にそれについて意見を交わすだろう。それが彼らのまったく新しい食体験にもつながる。こういう小さな取り組みが、子どもたちの食への関心を膨らませたり、新たなことに目を向けさせたりすることになるのだ。
また、誕生日を迎える子どもには誕生日パーティーを用意し、特別に「バースデープレート」と呼ぶ料理を提供する。子どもに希望の食事をリクエストしてもらい、それを献立にするのだ。パーティー用のホールケーキも準備する。子どもにしてみれば1年で唯一自分の希望通りの食事を作ってもらえる大切な日だ。それによって、自分は施設に受け入れられているのだと実感する子もいるだろう。
梶氏は言う。
「調理スタッフはできるだけ美味しいものを提供したいと思って作っていますが、子どもたちの中からは、これは苦手だとか、もっと量を増やしてほしいという声も出てくることがあります。ただ、私がそれでいいと思っているんです。うちにいる子どもは、家庭ではそういう言葉を発することさえ許されてこなかった。文句を言った途端に殴られるような環境で育った子が多い。
だからこそ、ここでは彼らが感じたことをそのまま言葉にしてほしいと思っているのです。たとえ、それが『まずい』『少ない』という言葉であっても、私たちが『今度は味付けを変えようね』とか『もっと量を増やすように気をつけるね』と応じてあげれば、彼らは主張を聞いてもらえたという安心を得られるのですから」
虐待家庭で育った子どもは、自分の言葉に耳を傾けてもらえなかった経験をしている。それが彼らの人間不信につながっていることもある。梶氏はそれをわかっているからこそ、食事について率直な感想を言ってもらえるような空気を作りたいと考えているのだろう。
とはいえ、施設では予算が決まっているので、いくら食の面から子どもたちを応援したいと願っていても、無尽蔵に豪勢な料理を提供できるわけではない。先のバースデープレートにしても、子どもの要求をそのまま叶(かな)えるのではなく、あらかじめ実現可能な料理を示し、その中から好きなものを選んでもらう仕組みだ。
限られた条件の中で、施設として何を優先するかを決めるのも調理スタッフの役割である。その中で梶氏が重視するのは、“心のこもった手作り料理”であることだ。
梶氏には忘れられない思い出がある。
子どもたちも高校生くらいになれば、弁当の中身の味より見え方を気にするようになる。ある女子高生は、学校に持っていくお弁当箱が安価なもので、どこにでもある銀カップに盛られていることに引け目を感じていたそうだ。友達がかわいらしいお弁当箱やカラフルなカップを用いているのがうらやましかったらしい。
梶氏はそのことを愚痴る彼女に同情したが、弁当箱やカップにお金を費やすより、中身を大切にしたいと考え、あえてそのままにした。ある日、学校で女子高生が友達にこうつぶやいた。
「かわいいお弁当でいいな。私も、そういうのがいい」
すると、友達はこう答えた。
「たしかにかわいいかもしれないけど、中身は全部冷凍食品だよ。あなたのは全部手作りでしょ」
女子高生はこれを聞いて、施設の弁当に誇りを持つようになったという。






