切り絵歳時記 ~柳田國男『先祖の話』から~ 11月 文/切り絵 ルポライター・切り絵画家 高橋繁行
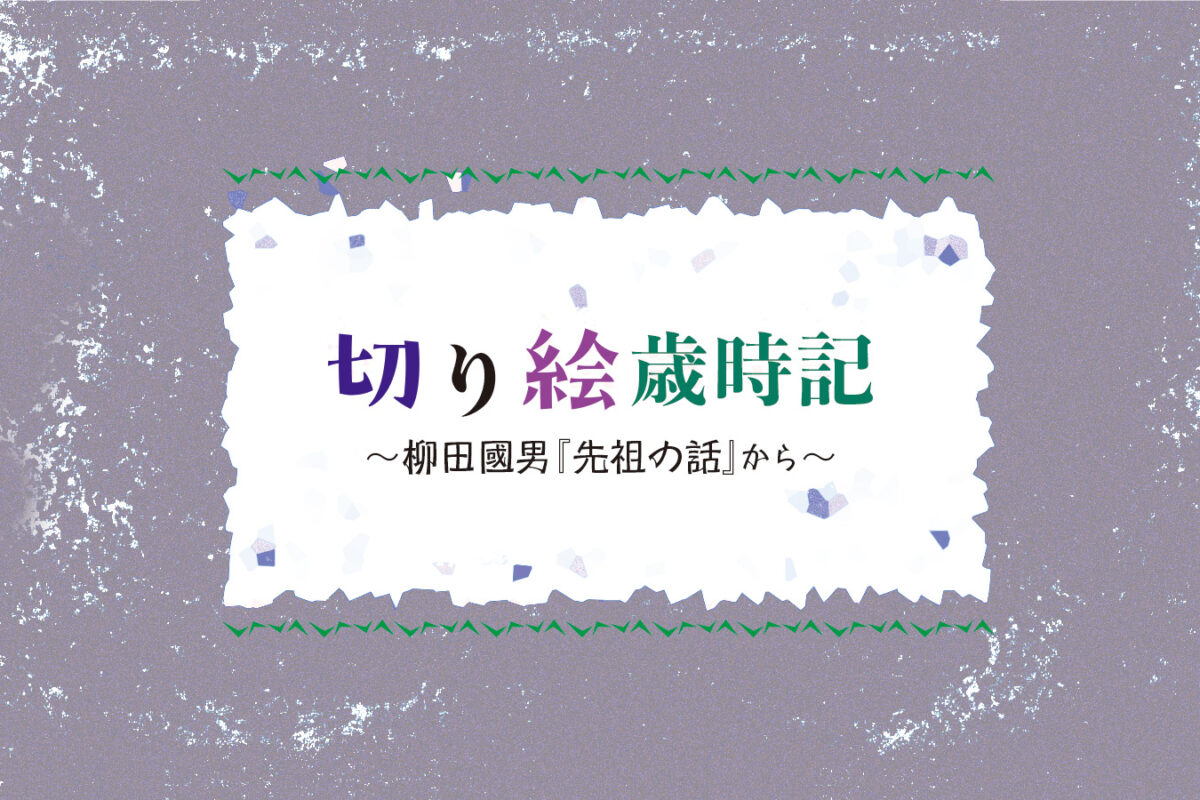
人は死ねば子孫の供養や祀(まつ)りをうけて祖霊へと昇華し、山々から家の繁栄を見守り、盆や正月に交流する――柳田國男は膨大な民俗伝承の研究をもとに日本人の霊魂観や死生観を見いだした。戦時下で書かれた柳田國男の名著『先祖の話』をひもときながら、切り絵を使って日本古来の歳時記を絵解きしたい。
お参り墓
旧暦十一月二十三日から二十四日にかけて行われる「大師講」は、家々で小豆粥(あずきがゆ)を供えて弘法大師(空海)をお迎えする民間行事だ。大師様の供養にちなみ、大切な人を偲(しの)ぶ意味でお墓の話をしよう。
テノール歌手の秋川雅史さんが歌い大ヒットした「千の風になって」は墓を否定する内容でけしからんとの声が一部で上がったが、故人の魂が大空を駆け巡るという歌詞は人々の心を鷲掴(わしづか)みにした。
死んで間もない荒忌(あらいみ)のみたま(霊魂)は、どこに留(とど)まるのだろうか。『先祖の話』では、墓の風習を通して触れている。

【お参り墓】
同書では「墓所(むしょ)がまた一つの屋外の祭場であって、(中略)もとは荒忌のみたまを別に祀(まつ)ろうとする、先祖の神に対する心づかいから、考え出された隔離ではなかったか」と問いかける。つまり、亡くなったばかりの荒忌のみたまを祀るために、新精霊と先祖の神様の住処(すみか)を、別々の場所に〝隔離〟していたという。これは死の穢(けが)れを嫌う先祖の神様に対する心遣いから生まれたものとされた。
新旧みたまの隔離のために、遺体を埋める墓と遺族が墓参りするための墓に分ける「両墓制」という風習があった。
亡くなって最初に遺体を埋葬する墓を「いけ墓・上の墓」または「棄(す)て墓」と言い、「喪(も)の穢れ」を含む場所とされた。これに対してお参り墓は別の所にあり、「祭り墓」「寺墓」と呼ばれた。そこは荒忌のみたまが昇華し穏やかになった霊を祀った場所で、同書は「多くは寺に托(たく)しまた参拝に都合のよい設備をしている」と解説する。現代人が先祖を弔い感謝を捧げるお墓だ。
柳田國男は、この墓の風習について「仏教の教化の行き渡るよりも前から、家には世を去った人々のみたまを、新旧二つに分けて祀る方式があり、またその信仰があった」と説いている。
プロフィル

たかはし・しげゆき 1954年、京都府生まれ。ルポライター・切り絵画家。『土葬の村』(講談社現代新書)、『お葬式の言葉と風習 柳田國男「葬送習俗語彙」の絵解き事典』(創元社)など、死と弔い関連の著書を手がける。高橋葬祭研究所主宰。






