カズキが教えてくれたこと ~共に生きる、友と育つ~ (5) 写真・マンガ・文 平田江津子
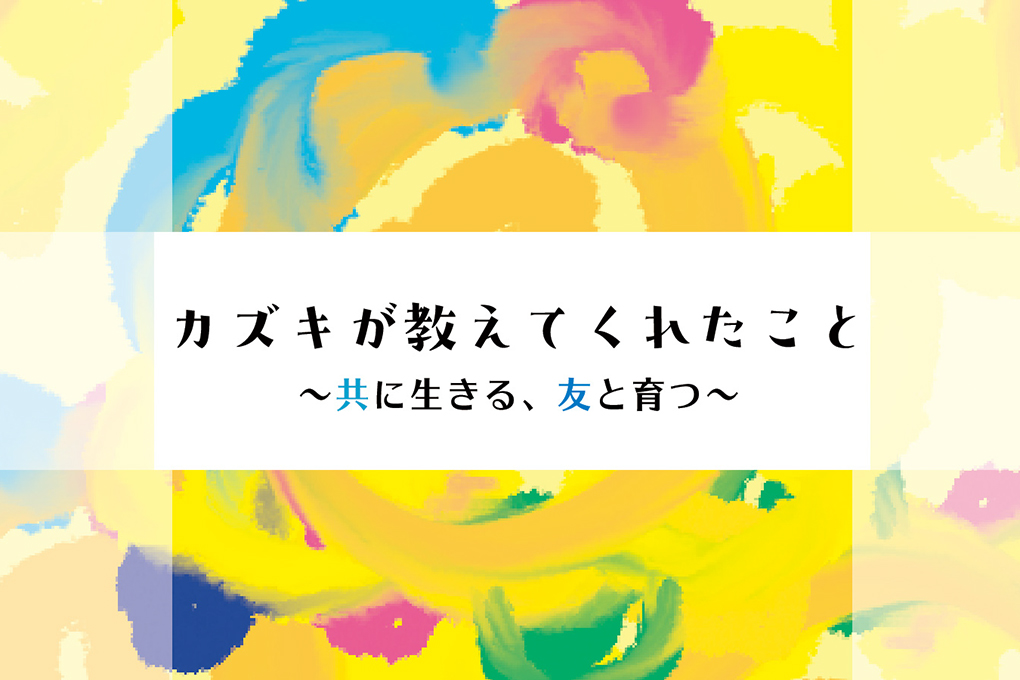
数々の出会いが導いた市民団体の設立
カズキが地域の小学校で特別支援学級に在籍していた時、普通学級で多くの時間を過ごさせてほしいと相談し続けました。でも、学校側は「別室での個別学習の方が彼の力を伸ばせる」と主張を曲げず、私たち夫婦は悶々(もんもん)とした日々を過ごしていました。

2014年、日本は「障害者の権利に関する条約」に批准しました。条約には、すべての子どもが分け隔てなく、地域で共に生き、学び育つ、いわゆる「インクルーシブ教育」が規定されています。それを知った私は、今の教育現場との乖離(かいり)にがくぜんとしました。「これはなんとかしなくては!」と思っていた翌15年冬、映画「みんなの学校」の存在を知りました。舞台は、実在する大阪市立大空小学校。そこでは、重い障害の子、気持ちのコントロールが難しい子など、多様な子どもたちが同じ教室で学んでいます。児童、教員のみならず、地域住民や保護者もいっしょに関わり、悩み、葛藤しながら向き合っていく中で、誰もが通い続けられる学校の教育実践を追ったドキュメンタリー映画です。
私たち夫婦はこの映画に感動し、「一人でも多くの市民に観(み)てもらって、真のインクルーシブ教育を知ってもらいたい!」という思いに駆られ、仲間と上映会実行委員会を立ち上げました。当日は予想をはるかに上回る人が訪れ、「感動した! こんな学校が増えたら日本が変わる!」という感想でアンケートはあふれていました。その多くの声に背中を押され、インクルーシブ教育の普及を目指す市民団体「障害児も地域の普通学級へ・道北ネット」が16年に立ち上がりました。

講演に立つ平田さん
主な活動は、障害のある子どもが地域の学校に就学する時、また学校生活を送る時に起こるさまざまな相談を受けます。「お話し会」を定期的に開き、障害児保護者のみならず、このテーマに関心のある人たちで互いの思いを聞き合う時間を大切にしています。さらに、研究者を呼んだインクルーシブ教育に関する講演会、学習会などのイベントも開催。行政に向けては、市長・教育長宛てに「インクルーシブ教育推進」のための要請書を提出し、話し合いの場を設けたり、市議会を訪れて会派を超えた議員さんたちと意見交換をしたりする活動を続けています。
開祖さまのご著書『この道』に、こんな一節があります。「人間関係の出発点は、何よりもまず出会うことだ。出会いがあってこそ語りあいができる。語りあって初めて、たがいの理解が生まれる。ほんとうに、たがいを理解しあうことによって信頼が生まれ、愛情がわいてくる。たがいに心から信頼しあい、愛情で結ばれるようになってこそ協力態勢ができあがるのである」――。活動にあたって、私はこのお言葉を胸に、人との出会いを大切にしています。
プロフィル

ひらた・えつこ 1973年、北海道生まれ。1男3女の母。立正佼成会旭川教会教務部長。障害のある子もない子も同じ場で学ぶインクルーシブ教育の普及を目指す地元の市民団体で、同団体代表である夫と二人三脚で取り組みを進めている。






