学林大樹オープンキャンパス 1泊2日の学林体験記

ハンガリアン・ユニテリアン教会の宗教指導者を招いて行われた対話の時間。「宗教の寛容」の歴史について学びを深めた
立正佼成会の学林は、「実践的仏教」「諸宗教対話・協力」を柱とする教育機関として創設された。中でも「大樹」は、人々を導く実践的仏教指導者や世界平和に貢献するリーダーの育成を目指している。学林は8月23、24の両日、大樹生が何を学び、どのような日常を送っているかの一端を体験するプログラム「学林大樹オープンキャンパス」を学林青梅キャンパス(青梅練成道場)で開催した。学林取材歴3年となる筆者も、この機会に大樹の魅力を五感で確かめようと、青年たちに交じって参加した。(A記者)
講義

オープンキャンパスの冒頭では、杉野学長が学林の柱である「実践的仏教」「諸宗教対話・協力」の精神を紹介した
23日午後1時。地面を焦がすような日差しの中、20代の学生をはじめ8人の参加者が青梅に集った。「自分の知見を広めたい」「講義での学びが楽しみ」――一人ひとりの抱負を杉野恭一学長や学林生が温かく受けとめ、オープンキャンパスが始まった。
1日目の冒頭を飾るのは講義体験。この日限りの特別講義として、熊野隆規教団理事長が『縁起観』(オンライン)、小池俊雄東京大学名誉教授が『自然科学』と題してそれぞれ教壇に立った。
このうち小池氏は、国内で頻発する豪雨災害に対処するには、防災、減災の取り組みを通した被災からの回復力の向上と、高齢化など社会の変化を踏まえた持続可能な開発の両立が求められると説明。そのためには地域社会と科学者が協力し合うことが不可欠だが、両者の持つ知識や考えの隔たりは大きく、議論に困難が生じているという。

小池氏の特別講義では、参加者との活発な質疑応答が行われた
「社会と科学の間にある溝をつなぐのは皆さんです」。真剣な表情で語る小池氏は、地域の人々と科学者の間に立つファシリテーターとして、両者と信頼関係を築き、課題や解決策の議論につなげる“触媒”になってほしいと期待を寄せた。
〈対話によって分断を超え、平和をつくる宗教者の役割と似ている〉。今年7月に取材した東京平和円卓会議でも、相互理解によって困難な課題に取り組む世界の宗教指導者たちに出会ったことを回顧した。この世の全ては網の目のようにつながっているのだと、学林の教養を支える深い仏教観に思いをはせた。
寮生活

大樹寮での食事当番体験。和気あいあいとした雰囲気の中、24人分の麻婆豆腐を作り上げた
四季を彩る草花や野原を駆ける動物、そして学林生が耕す水田。自然の恵みにあふれる青梅の山の麓に、学林生が寮生活を送る「大樹寮」がある。
午後6時過ぎ。寮の台所にエプロン姿の食事当番(食当)が集ってきた。手際よく豆腐やねぎなどの食材を調理していく。寮では献立の考案や買い出しも含め、学林生が当番制で食事を作る。この日は参加者も食当を体験し、鍋いっぱいの麻婆豆腐やサラダを完成させた。
総勢24人のにぎやかな夕食後、参加者たちに一日の感想を聞くと、「堅苦しい雰囲気を想像していたけど、学林生がみんな話しやすくて安心した」と口をそろえた。大樹生と共に寮で暮らすインドやバングラデシュ、アメリカ出身の蓮澍生も、日本の仲間や参加者と分け隔てなく語らっていた。

学林青梅キャンパスのある青梅練成道場は1966年に開設。次世代を担う青少年育成の場として活用されてきた
その一人、蓮澍・海潮音科31期生のボルア・スミさん(26)=バングラデシュ教会=は、寮生活で得た学びをこう語る。
「土を耕し、植えた稲が育っていくのを見ると、おいしい料理を作ってくれた故郷の母親や、いのちを分けてくれた動植物への感謝が湧きます。異なる人や文化に合わせるのはとても大変ですが、教えを学び実践することで、精神的な成長を実感しています」
確かに、寮の運営を話し合う学林生たちを見ると、話し方も身ぶりの仕方も皆異なり、意見がぶつかる瞬間もある。それでも「どうすれば良いか」と考え、笑顔を忘れずに議論する姿は、互いの差異を“仏性”として尊び讃(たた)える証拠だと感じた。
宗教対話

青梅に到着したハンガリアン・ユニテリアン教会の一行と笑顔であいさつする参加者たち
爽やかな朝の空気に包まれた24日午前8時。寮での読経供養と朝食を終えて向かった東棟に、本会と交流の深いハンガリアン・ユニテリアン教会(ルーマニア)のイシュトヴァーン・コヴァーチ司教ら4人が到着した。行われたのは、二日間を締めくくる「世界の宗教指導者との対話」だ。
海外ゲストを前に緊張する一同に対し、コヴァーチ司教はにこやかに語り出す。「(同教会のある)トランシルバニアは、宗教の寛容が勅令として明文化された土地です」。
古くからカトリックや正教会などが共存してきたトランシルバニアでは1568年、ユニテリアンを含むキリスト教4宗派の信徒に信教の自由が認可された。自身の信仰が政治や他宗派に介入されずに守られる環境は、当時極めて画期的だった。司教らは、同教会が「宗教の寛容」を尊重し、宗教協力や青年教育に取り組んできたと説いた。
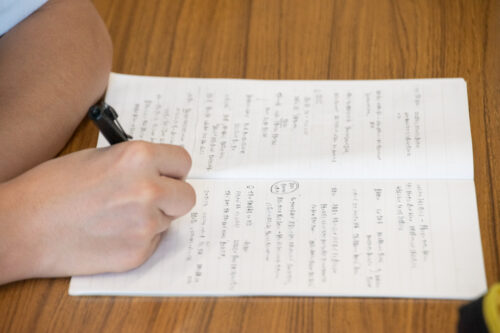
世界の宗教指導者との出会いをかみしめ、一人ひとりが気づきや学びをノートに書き留めた
「宗教協力は、平和実現のためにどのような役割を果たしますか」という参加者の質問に、司教は「紛争解決の一番の架け橋はコミュニケーションです」と応答。自らの教義に固執せず、互いの共通性を見いだす大切さを伝えた。「平和はあなたから始まります」と穏やかに話す司教の姿から、諸宗教対話・協力に生涯をかけた庭野日敬開祖の精神を感じた。
宗教対話の時間を楽しみにしていたというS・Hさん(21)とS・Nさん(21)兄弟=北教会=は、「ユニテリアンの方々の話を聞き、開祖さまが示された“万教同根”という言葉を思い出しました」「世界の人々と信仰を語り合うなど、自分もスケールの大きな行動をできるようになりたい」と、世界とつながる学林教育の魅力をかみしめた。
1泊2日の体験を通し、「世界の佼成会たらん」と学林創設を決意した庭野開祖の真意に少しだけ近づけたように思う。世界平和と人類全体の幸福を目指すには、世界を見通す広い視野と寛容な心が欠かせない。その精神は、大自然の中で送る学林生活を通し、互いを理解して人格を磨き合いながら、学林生一人ひとりが育てていくのだろう。






