切り絵歳時記 ~柳田國男『先祖の話』から~ 10月 文/切り絵 ルポライター・切り絵画家 高橋繁行
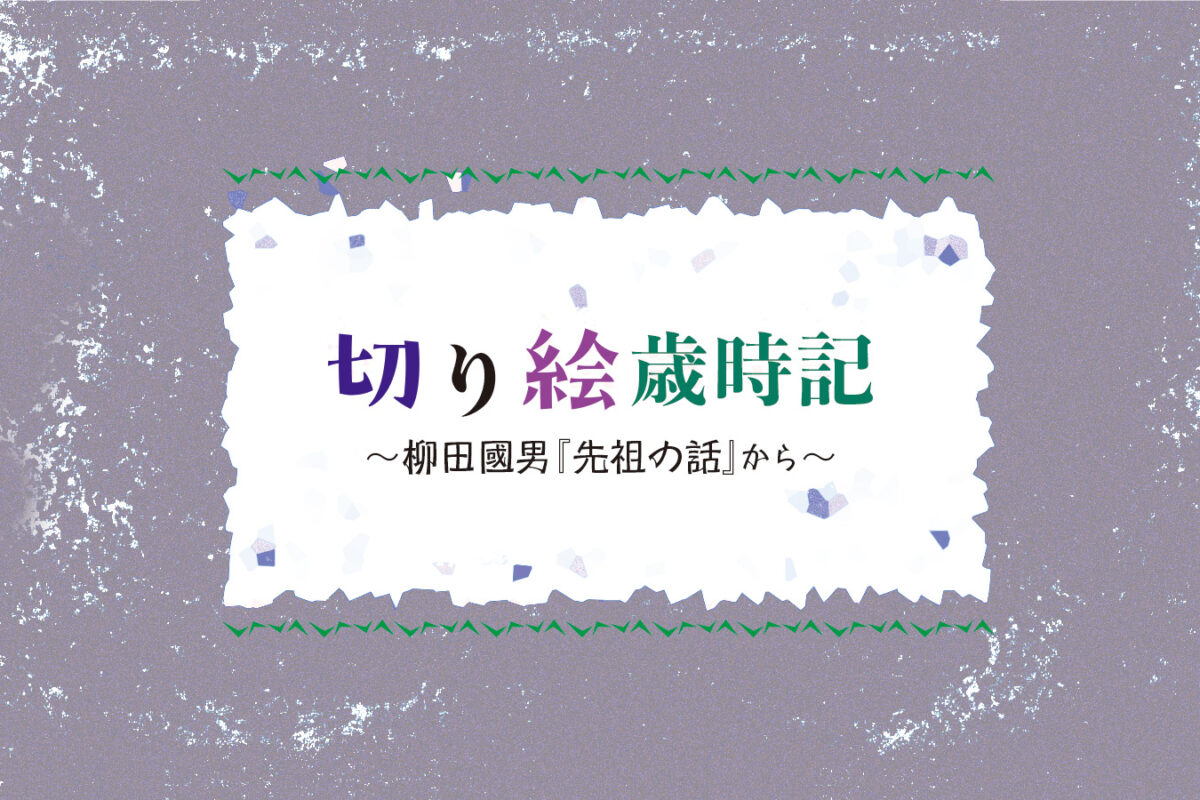
人は死ねば子孫の供養や祀(まつ)りをうけて祖霊へと昇華し、山々から家の繁栄を見守り、盆や正月に交流する――柳田國男は膨大な民俗伝承の研究をもとに日本人の霊魂観や死生観を見いだした。戦時下で書かれた柳田國男の名著『先祖の話』をひもときながら、切り絵を使って日本古来の歳時記を絵解きしたい。
山神祭
春は「山の神」が里に降(くだ)って「田の神」になり、秋の終わりにはまた田から上って、山に還(かえ)って「山の神」になるとよく言われる。『先祖の話』は、「日本全国北から南の端々まで、そういう伝えの無いところの方が少ないと言ってもよいほど、弘(ひろ)く行われている」と述べている。
また、「一年に両度、春は来り冬は還りたまうという一定の去来の日があること」を「多くの農村では山神祭、もしくは山の講の日などというのである」と説いている。山の講は、春は旧二月、秋は十月ないし十一月に行われ、山の神様を祀(まつ)り、男は一日中、山仕事をしないというような行事が行われると言う。
この山の神・田の神の交代劇の言い伝えが広く全国に存続したのは、どうしてだろうか。柳田國男は、一年の四分の一だけ山で休憩なさる山の神以上に、一年の四分の三、豊穣(ほうじょう)を願い、里に出て田のほとりから見守る田の神様に対する農民の深い思い入れがあったことを、言い伝えが各地に分布した理由に挙げている。

【収穫祭】
数ある農作物の中で「稲」は唯一の卓越した重要性を持ち、君(天皇)と神への供御(くご=供え物)として必ず奉った。その生産には、苗代の準備、田植え、稲刈りといった人の力以上に、「水」と「日の光」という天の恵みに頼る部分が大きかった。
古来伝わる「児孫のために美田を買わず」ということわざは、財産を残すと、子孫がそれに頼って努力しなくなるから残すなという教訓だが、田の神への思い入れが深い農民には「先祖の美田を守りたい」との気持ちが強かったのではないか。それは子や孫のために、田を耕し豊穣な実りを得たいという切実な願いからだろう。
田の神は「御田の神」、または「農神(のうがみ)」、「作の神」とも呼ばれ、「祀る人々の先祖の霊であったろうか」と柳田國男は想像している。先祖の霊ならば、先祖代々の家を守る、重要な神である。
田の神が先祖の霊なら、この田の神・山の神、一年に二度の交代劇を、われわれの先祖のみたまを祀る魂祭(たままつり)として大切に祀らねばならない、ということなのだろう。
プロフィル

たかはし・しげゆき 1954年、京都府生まれ。ルポライター・切り絵画家。『土葬の村』(講談社現代新書)、『お葬式の言葉と風習 柳田國男「葬送習俗語彙」の絵解き事典』(創元社)など、死と弔い関連の著書を手がける。高橋葬祭研究所主宰。






